開催内容 桂冠塾【第100回】
『野火(のび)』(大岡昇平)
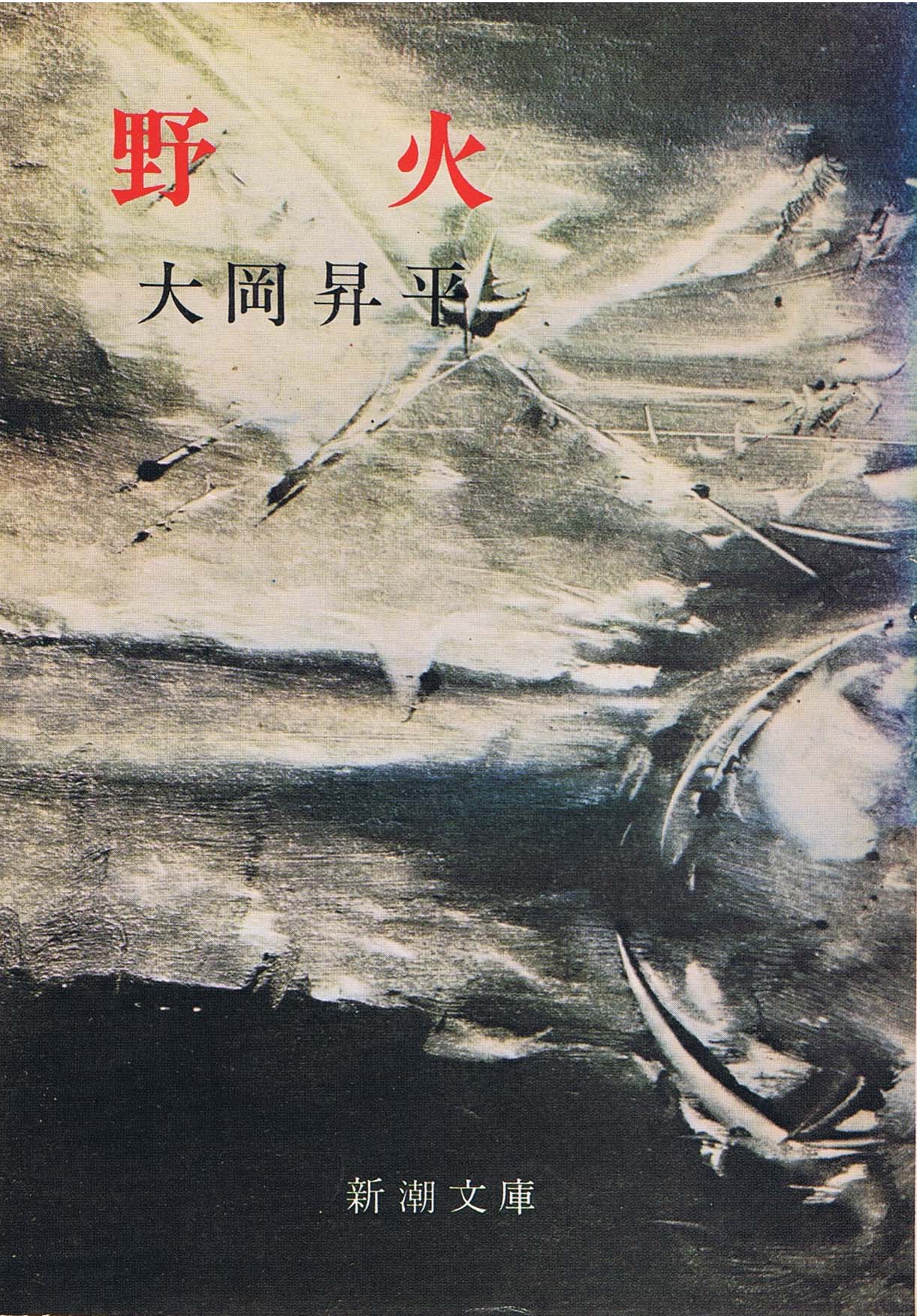
| 開催日時 | 2013年6月29日(土) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 勤労福祉会館 和室(小) 西武池袋線大泉学園駅・徒歩3分 |
開催。諸々コメント。
今回で100回目の節目を迎えました。各回に参加いただきました皆様に感謝申し上げます。
様々な名著に触れながら互いに研鑽しあう場として2005年4月に始めた桂冠塾の取組み。毎月1回、1冊の本を取り上げて参加者の方々と共に読み、語り合って一つの区切りを迎えました。
特に100回記念イベントを行なうわけではありませんが(^_^;)これからも地道に続けていきたいと思います。
太平洋戦争の激戦地
作品は昭和19年11月末にレイテ島に上陸した日本陸軍の田村一等兵の独白の形で構成されています。レイテ島とその周辺海域は、太平洋戦争最大の激戦地のひとつです。
1944年10月20日ダグラス・マッカーサー率いるアメリカ軍がレイテ湾に上陸。
レイテ島がフィリピン戦線の主戦場として攻防が繰り広げられます。
物量に勝るアメリカ軍は日本軍の物資と兵員の補給路を完全に断ち、孤立した8万人余りの日本軍兵士がほぼ全滅するという惨劇の結末を迎えました。レイテ島からの生還率は3%ともいわれています。
大岡昇平氏は自らの従軍体験を元に、この作品を書き上げています。
精神の極限
主人公田村一等兵は以前から罹患していた肺病が悪化し野戦病院に行かされますが、受入れできない病院から拒否され、部隊からも放逐されてレイテ島の山野を彷徨します。日本軍がパロンポンに救出に来るという軍命令を伝え聞き、多くの日本兵が分断された道なき道をパロンポンに向かいます。 人が目の前で次々と死に、腐敗した死体が散乱する極限状態の中で、田村は自らの生への執着と絶望の狭間を行き来し、精神的にも異常な状態に陥っていきます。
自らが生き延びるために現地人の女を殺傷した田村。 そしていつしか田村の目は屍体の臀肉を追っていた。 そして同僚が食料として「猿」を狩猟して食する場面に至って、田村は自身の精神的均衡が崩壊することを悟ります。
日本兵による人肉食
この作品が注目された理由として第一に挙げられるのは、日本兵による人肉食が描かれている点にあります。作品の中では、田村一等兵が懺悔もしくは生への執着が消えた虚脱の思いから、一旦は全ての生あるモノを口にすることを拒絶するシーンが描かれます。
その直前、田村は飢餓と狂気によって屍体の臀肉を食する欲望に屈しかけます。それを押し止めていたモノは理性でも神への信仰でもなく、見られているかもしれない「人の目」でした。
森に散在している臀部の肉が削ぎとられた屍体は、ある事実を田村に語りかけるわけです。
そして田村は、死ぬ直前に「食べてもいいよ」と言い残した日本兵の屍体を、人目の付かない場所に移動します。
それでも食べることができない。「食べていいよ」という言葉が禁圧として働く。 おれは本当に食べるのか。 蠅がたかって屍体が見えなくなると安堵した。 山蛭が太っていく。 田村はその屍体の血で太った山蛭を押しつぶして血をすすった。 田村は思う。 人の屍体を食べることと、山蛭と介して血をすすることに違いがあるのかないのか。違いなどないではないか。
田村は屍体の肉を食しようと右手に剣を握る。 その瞬間、その右手を田村の左手が押し止めたのである。 「汝の右手のなすことを、左手をして知らしむることなかれ」 田村が聞いたのは自身の心の声なのか、それとも天か神の声だったのだろうか。 その後田村は、一切の草木すら口にせず、死んでいくだろう運命に身を任せようとします。そんなときに以前行動を共にしていた日本兵永松に抱き起こされます。
田村は、永松の水筒の水を飲み、差し出された「猿」の干し肉を食べた。 決意していた禁欲はどこかに消え去っていた。 そして後日、田村は知ることになる。 その「猿」とは人間のことであるという事実を。 さらに永松が「猿」を狩猟する場面に遭遇する。周囲には足首や食に適さない人の部位が切り捨てられていた。
そして自分達二人の食料にするために目の前で同僚の殺人を行い手首と足首を打ち落とした永松に、田村は銃口を向ける。
田村の記憶は、ここで途切れている。 田村はアメリカ軍の俘虜病院に収容され、敗戦後の昭和21年3月に復員。5年後に東京郊外の精神病院に入り、今こうしてこの手記を書いている...。
そんな結末に至ります。
食べてよい生命と食べてはいけない生命があるのか
その当時を実際に見ていない私達は、人肉食の事実があったのかどうかを論じることは避けたほうがよいのかもしれませんが、現在残っている様々な手記や文献から推察すると、太平洋戦争末期において日本兵による人肉食が行われたことは事実を考えるのが妥当なのだろうと思われます。ただ、その事実(と思われる)の是非を論じることが主眼ではない。 人肉を食べてまで生き延びることが是なのか。 もし人肉は食べていけないとすれば、人肉の血で太った山蛭から絞って血を飲むことは許されるのか。 さらには、人間が生きていくために多くの生ある動物を食べていいのか。 もっと言えば、動物がだめで植物ならいいのか。 現実は何も食べなければ、人は生きていけない。 なにがしかの形で、他の生命を食して自分自身の生命を長らえているのである。 食べていい生命と、食べてはいけない生命という区分はあるのか。 生命にそうした差異や価値の違いがあるのだろうか。 真正面から、生きていくということの根本命題を顔面に投げつけている。 それがこの作品の本質ではないかと感じます。
キリストの声を聞いた田村
作品の中で大岡昇平氏は、田村一等兵に人肉食を思いとどまらせた要因はキリスト教の信仰であると思わせる文脈を綴っています。大岡昇平氏がキリスト教徒であることは知られた事実であるし、作品中でも個人の快楽や生への執着に対して「デ・プロフンディス(われ深き淵より汝を呼べり)」tの聖書の一節で警句を鳴らすシーンを描き、最終章においては戦場の赴いたことも含めて、様々な体験は全て神が彼に与えた試練であると田村が気づくというストーリーとも読める。
だから最終行が「神に栄えあれ」の一文で締めくくられているのだとも読めると思います。
それが大岡昇平氏の意図であるとすれば、田村一等兵は人肉食という地獄の淵から覗いていた悪魔の誘惑に勝ったことになるでしょう。
大岡氏を含めて、極限の地獄絵の渦中にいた者は、そう考えるしか逃げ道がないのかもしれない。
ではその一線を越えて、人肉を食べてしまった者はどうなるのでしょう。
キリスト教の説く深き淵の地獄に堕ちてしまったのでしょうか。
キリスト教の説く人間の限界
ある意味、キリスト教の説く教義はシンプルです。神(地球を創った創造神)が自らの姿に似せて作ったのが人間であり、人間に地上の万物を支配する使命を与えたとされています。一方、人間以外の生物や自然といった万物は人間の支配物であるので人間が生きていくなかで利用することが許されているとなります。
そうした考え方が根底にあるので、一応は人間が人間を殺傷することは罪となります。 しかし、そこには一定の条件があります。
その人間が神の意志に背いていない限りという大前提条件です。
もし神の意志に背いた人間がいれば、それは認める価値はない。
そうした論理に至るのは、ある意味で必然とも言えるでしょう。
だからキリスト教徒でない者を殺生することが聖戦の名のもとで延々と行なわれてきましたし、邪教徒として一番最初に地獄に落ちる(辺獄を漂う)とされてきました。
作品の背景となる日本軍は、当然のことながらキリスト教の教義を根底にした軍隊でも国家でもありません。したがってキリスト教観では敗戦するのは当然として、その中でキリスト教的信仰を貫いた田村一等兵は聖者賢人とも位置付けられるかもしれません。
さらに言えば、もし仮に人を殺して人肉を食べていたとしても、異教徒である日本兵の人肉であれば問題なしとされるかもしれません。
確かに田村を精神的極限状態から救ったのはキリスト教の信仰だったのだろうと思いますが、キリスト教を信仰しない者や現代を生きる私達にとって普遍的な人間の考えとはなりえない。
殺す心を殺す
このテーマを考えるとき、思い起こす興味深い釈尊にまつわる仏教の説話があります。ある人が釈尊に次のように質問しました。
「生命は尊厳であるというが、人間は誰しも他の生き物を犠牲にして食べないと生きていけない。いかなる生き物は殺してよくて、いかなる生き物は殺してはいけないのか?」
まさに『野火』が問いかけるテーマでもありますが、それに対する釈尊の答えは次のようであったと言います。
「それは殺す心を殺せばよいのだ」
この答えを詭弁だとか論点をすり替えていると言う人もいるかもしれませんが、私はそうだとは思わない。何のための食なのか、その食を得た自分自身がいかように生きようと思っているのかという自分自身の内面こそが、その殺生の是非を決めるということではないかと思います。
かつてこの説話について論じた平和思想家の池田大作SGI会長は次のように記しています。
暴力や殺生などの錯綜した事象は、おびただしい位相を持ち、どの線が良く、どの線が悪いなどという一律な線引きなど不可能である。
ゆえに「殺す心を殺す」こと、外面的な理非曲直よりも、まず内面の制覇こそが、第一義的な重要事なのだ。
その「自己規律」の心が確立されていれば、いかなる迷いや逡巡も乗り越えて、最善の選択、決断を過たぬはずである--。
釈尊の真意も、ここにあるはずである。
(2002年1月26日・第27回SGIの日記念提言)
限界の状況に対して過たない判断をいかにして下すか。
それは自分自身の中に自己規律の心を確立することによって成し遂げられる。
“この場合はAですよ”“このケースはBなんですよ”というようなマニュアル的な解決方法は、現実の人生には何の役にもたたない。
私達は経験的にわかっているはずですが、ややもするとマニュアル的な答えを欲しがってしまう。
その安易な生命の傾向こそが、私達が乗り越えるべき課題ではないかと思います。
『野火』は、現代を生きる私達に生きていくための自己規律は確立しているかと疑問を投げかけているのかもしれません。
作者
大岡 昇平(おおおか しょうへい)1909年(明治42年)3月6日 - 1988年(昭和63年)12月25日
小説家・評論家・フランス文学の翻訳家・研究者。
明治42年東京市牛込区新小川町に株式仲買店に勤める父・貞三郎、母・つるの長男として誕生。
10歳の時、「赤い鳥」に童謡を投稿して入選する。
青山学院中等部に入学。この時期にキリスト教の感化を受ける。成城中学校4年に編入(成城高等学校(7年制)に再編)。アテネフランセでフランス語を学び、小林秀雄からフランス語の個人教授を受ける。京都帝国大学文学部文学科に入学。河上徹太郎、中原中也らと同人雑誌「白痴群」を創刊。昭和7年3月卒業。
国民新聞社、帝国酵素を経て川崎重工業の勤務時代の昭和19年3月に教育召集を受ける。徴兵検査で第二乙種とされて10年が経った35歳の時だった。3ケ月の兵役訓練を経て、7月にフィリピンのマニラに到着。ミンドロ島警備の暗号手としてサンセホに赴く。
昭和20年1月、米軍の捕虜となりレイテ島のタクロバン俘虜病院に収容される。敗戦後の同年12月に帰国。
昭和24年『俘虜記』、昭和27年『野火』を刊行。その後『花影』『レイテ戦記』『中原中也』『事件』『小説家夏目漱石』等多数の作品を発表。
1988年(昭和63年)12月25日逝去。
文壇有数の論争家で、特に史実に忠実であることを信条としていたと思われる。井上靖の『蒼き狼』、海音寺潮五郎の『二本の銀杏』『悪人列伝』、松本清張の『二本の黒い霧』、江藤淳の『漱石とアーサー王伝説』、森鴎外の『堺事件』などを批判した。
推理小説の愛読者でもあり、1950年代には海外推理小説『赤毛のレッドメーン』(イーデン・フィルポッツ作)や『すねた娘』(E・S・ガードナー作)を翻訳、自らも推理小説を執筆して、とりわけ『若草物語』の題で連載し、後に『事件』と改題した作品は日本推理作家協会賞を受賞し、映画やテレビドラマになるなど、高い評価を受けている。
また、河上徹太郎、小林秀雄らの愛人で、白洲正子の友人だった坂本睦子を8年あまり愛人とし、妻の自殺未遂騒ぎを何度か経た後に睦子と別れた。翌年睦子が自殺。その後彼女をモデルに『花影』を書き、新潮社文学賞と毎日出版文化賞を受賞。高見順は、肝心の大岡自身の苦悩が描かれていないと批判、白洲正子も睦子が描かれていないと批判している。
作品の章立て
1.出発2.道
3.野火
4.坐せる者等
5.紫
6.夜
7.砲声
8.川
9.月
10.鶏鳴
11.楽園の思想
12.象徴
13.夢
14.降路
15.命
16.犬
17.物体
18.デ・プロフンディス
19.塩
20.銃
21.同胞
22.行人
23.雨
24.三叉路
25.光
26.出現
27.火
28.飢者と狂者
29.手
30.野の百合
31.空の鳥
32.眼
33.肉
34.人類
35.猿
36.転身の頌
37.狂人日記
38.再び野火に
39.死者の書

