開催内容 桂冠塾【第49回】
『二都物語』(ディケンズ)
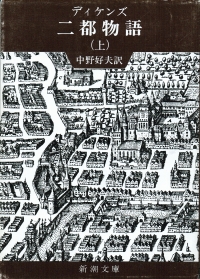
| 開催日時 | 2009年4月25日(土) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 勤労福祉会館 第二和室 西武池袋線大泉学園駅・徒歩3分 |
開催。諸々コメント。
今月はディケンズ作『二都物語』を取り上げます。発表されたのは1859年。物語の舞台はフランス革命前夜ですが、いわゆる歴史小説ではありません。
かつて英語の教科書や副読本に取り上げられる常連の作品でもあったことからイギリスの好きな作家としてディケンズの名前が挙がることも多いようにも思います。
フランス貴族出自を隠してイギリスに暮すチャールズ・ダーニーと、鬱積した人生を送っていた若き弁護士シドニー・カートンが主人公です。
カートンは腕利きのストライバー弁護士と組んで酒を浴びながら次々と訴訟をこなす生活を送っている。
チャールズ・ダーニーとシドニー・カートンは容姿が似ていた。ストライバーとシドニー・カートンはそのことを事例として、チャールズ・ダーニーにかけられたスパイ容疑を晴らすことに成功する。
ダーニーは渡英する船でルーシーに出会う。彼女の父は18年間捉えられていたバスチーユ牢獄から出獄し、父娘でイギリスに帰る途上であった。
ダーニー、カートンの二人がルーシーに思いを寄せるところから舞台は大きく回転していきます。
ルーシーに求婚したチャールズに遠慮して人生に絶望し生活が荒れていたカートンは自ら身を引く。
幸せな暮しを始めたチャールズ夫妻であったが、かつて従者であったギャベール父娘が窮地に陥ったことを知り、自らの身の危険を省みず一路フランスに向かう。
彼の身を案じたルーシー親娘に付き従ってカートンもフランスに渡る。
ダーニーは裁判にかけられ...。
邦訳した中野好夫さんの辛口の書評に影響されたのか通俗小説と言われることもある作品ですが、世界で2億冊が読まれている作品。
その評価は各人が読了して考えてみるのがよいと思う一冊です。
世の中には瓜二つの人間がいる
物語は、フランス革命前から革命勃発後の時代に、フランスとイギリスを舞台に展開されます。ディケンズ独特の比喩的表現や意表をつこうとする伏線の敷き方には賛否が分かれるところですが、全体を通して引き込まれるような流れがあり、ストーリーテラーという言葉がしっくりくる作品に仕上がっているように思います。
小説の中心にいるのは、主人公二人のうち荒れた人生を送ってきた青年弁護士シドニー・カートンでしょう。
ただし前半部分ではカートンの描写はあまり多くはなく、むしろ、フランス郊外に土地を所有していた伯爵の地位を捨ててイギリス社会で生きようとするチャールズ・ダーニーにスポットが当たっています。
このダーニーがルーシーという美しい女性と出会うところから物語が大きく、華やかに展開していきます。
ダーニーが自分自身の身分を隠しつつ、祖国フランスに残してきた領民の管理等のためにかつての臣下と連絡を取っていたことが誤解され、スパイ容疑で死刑判決を受けそうになった裁判で弁護に当たったのが、敏腕若手弁護士のストライバー。
ストライバーと組んで仕事をしているのが前述のカートンです。
ダーニーの弁護の決め手は容姿がそっくりだったカートン自身でした。
いわば
「世の中には瓜二つの人間がいる」
「検察側の証人が『見た』という被告人が本人かどうか確定できるのか」
という論理展開です。
劇場的には受けるシーンでしょうが、現実の裁判の再現としては相当無理があります。論理の飛躍といえるかもしれませんが、この弁護によってダーニーは死刑から逃れることができます。
ダーニーとルーシー。ダーニーとカートン。
この裁判で大きく二つの感情が明白になります。ひとつは、ダーニーに不利な証言を行わざるを得なかったルーシーが登場しますが、そのことによってダーニーとルーシーの間で互いの愛情を意識したと思われること。
もうひとつは、容姿が瓜二つなのに、かたや愛と名声を勝ち得ていくダーニーと、堕落した人生から抜け出すことができないカートン。それを痛烈に思い知ってしまうカートンの存在。
このふたつの感情が、この物語のテーマに密接に絡み合っていきます。
カートン、再びダーニーを救う。
この物語の後半は、祖国フランスのかつての臣下がフランス革命の中で死刑に処せられる危機に陥っていることを知ったダーニーがフランスに渡り、反逆の徒として死刑に処せられそうになります。そのダーニーをカートンが身代わりになって助けるわけですが、この展開は前半の裁判と基本的には同じ構図で、比較的早い時点で推測できてしまいます。
この主たるストーリーに、いくつかの伏線的な話題や数多くの人間関係を絡めて物語としてのおもしろさを膨らませているというのが『二都物語』の全体像ではないかと思います。
ただいずれも場面場面での描写テクニック程度であり、人の深層部分に訴えかけるような類いのものではないと感じます。
特に、後半に描かれる樵(きこり)やドファルジュの奥さんは、かえって主題が何であったのかがぼやけているのではないかと思いました。
バスチーユ牢獄に幽閉されていたマネット博士
その一方で、マネット博士が18年間バスチーユ牢獄に幽閉されていたことは、後半部分で大きな山場を作り出す重要な要因になっていきます。これはこの作品中の最重要の伏線といえるでしょう。
幽閉に至る事件、幽閉中に書き残した書簡、牢獄北塔105号に掘り込んだ博士自身の壮絶な感情が、関係する様々な人間達の精神形成と行動に、重要な役割を果たしていきます。
もっと語ってほしい。未回収の伏線も。
ディケンズとしては歴史的な事件や理念信念といった類いを描くよりも、個々の人間達の感情表現や「こんな風に絡み合っていたんだ」というような意表をつく人間関係を描くことで、推理小説を読むような意外感、種明かしの楽しみを描きたかったのかも知れません。結果的により多くのことを描こうとして大活写的になったのか、元々娯楽作品として描こうとしたのか、その意図は不明ですが、もう少しテーマを絞り込んで掘り下げるか、紙数を増やして書き込んでいただきたかったなというのが、私の正直な読後の印象です。
・ダーニーはどうして貴族の身分を捨てたのか。その決断の出来事は何だったのか。
・マネット博士の不遇の半生と精神的発作との格闘。
・カートンはなぜ堕落した半生を送ってきたのか。なぜ弁護士の道を選んだのか。
・ルーシーはダーニーのどんなところに惹かれていったのか。
・フランス革命の渦中でどのような市民の愚行があったのか。
・貴族中心のヨーロッパ社会の悪弊と堕落はいかようであったのか。
・多くの庶民はどのような気持ちで生きていたのか。
・カートンはなぜダーニーの身代わりになったのか。
・カートンの行為にはどのような思いが込められていたのか。
・英雄視されるマネット博士の心の動きはどうであったのか。
・フランス革命を隣国イギリスの市民はどのように見ていたのか。
などなど...。
作品のタイトルである『二都物語』と大掛かりに思える舞台設定から、こうしたテーマが描かれていることを期待するのは、さほど無理な注文とも言えないと思うのですが、皆さんはどのように感じられたでしょうか?
壮大なエンターメント作品『二都物語』
こうした点を踏まえても、なお興味深く楽しんで読める作品です。それは、ディケンズが生まれ育った時代がフランス革命から数十年であり、革命の余韻がわずかでも感じられる環境であったのか、その後の社会にあってもディケンズ自身が社会の底辺に近い貧困生活を経験してきたことが、この作品にリアリティを与えているのかも知れません。
たとえば作品冒頭に出てくる駅馬車内での感情描写などは俊逸と言って過言ではないと思います。何が起こるのか、言葉では表現できない不安と陰謀のようなじめっとした匂いを読者である私達の多くは感じたと思います。
またこの描写によって、当時の社会がいかに荒んでいて、不安定であったのかが推察することができます。
全世界で2億人以上が読んだ『二都物語』。
まだ読んでいない方には、一度読んでみてほしい一冊です。
章立て
第一巻 よみがえった第一章 時代
第二章 駅伝馬車
第三章 夜の影
第四章 準備
第五章 酒店
第六章 靴職人
第二巻 黄金の糸
第一章 五年後
第二章 見世物
第三章 失望
第四章 祝い
第五章 山犬
第六章 何百という人々
第七章 パリでの貴族
第八章 田舎での貴族
第九章 ゴルゴンの首
第十章 二つの約束
第十一章 双幅の一枚
第十二章 粋人
第十三章 無粋者
第十四章 正直な商人
第十五章 編物
第十六章 編物は続く
第十七章 ある夜
第十八章 九日間
第十九章 専門医の所見
第二十章 訴願
第二十一章 足音はこだまする
第二十二章 波はなお高まる
第二十三章 火は燃えあがる
第二十四章 磁石は巌に吸い寄せられて
第三巻 嵐の跡
第一章 秘密に
第二章 回転砥石
第三章 暗い影
第四章 嵐の中の凪ぎ
第五章 樵夫
第六章 凱旋行列
第七章 扉をノックする音
第八章 カルタの手札
第九章 勝負
第十章 暗影の実体
第十一章 薄暮
第十二章 闇黒
第十三章 五十二人
第十四章 編物は終わる
第十五章 足音は永久に消える
主な登場人物
シドニー・カートンSydney Carton (法廷弁護士)ルーシー・マネット Lucie Manette (マネットの娘)
チャールズ・ダーニー Charles Darnay (フランス人・ルーシーと結婚する)
ドクトル・マネット Dr. Alexander Manette (医者・マネットの父)
ミス・プロス Miss Pross (ルーシー父娘の従者)
ミスター・ロリー Jarvis Lorry (銀行家)
ジェリー・クランチャー親子 Cruncher(テルソン銀行の使い走り)
ガベール Gabelle (元St. Evremonde侯爵の使用人)
マリー・ガベール Marie Gabelle (元St. Evremonde侯爵の使用人の娘)
ストライバー Stryver(有能な弁護士・シドニーの相棒)
ムシュー・ドファルジュ Ernest Defarge(パブの主人・元マネット医師の従者)
ドファルジュ夫人 Madame Terese Defarge (昔マネット医師に助けられた娘)
ジョン・バーサッド Barsad(Darnayを密告した小悪党・Miss Prossの弟)
田舎の侯爵閣下サン・テヴレモンド Marquis St. Evremonde(冷酷な仏貴族・Darnayの叔父)
ギャスパール Gaspard (St. Evremonde侯爵に子供を轢き殺された男)
作者
チャールズ・ディケンズ(Charles John Huffam Dickens)(1812年2月7日 - 1870年6月9日)は、イギリスのヴィクトリア朝を代表する小説家。ポーツマスの郊外に生まれた。年少時より働きに出され、新聞記者を勤めるかたわらに、作品集『ボズのスケッチ集(Sketches by Boz)』で登場。主に下層階級を主人公とし、弱者の視点で社会を諷刺した作品群を発表した。
その登場人物は広く親しまれており、イギリスの国民作家とされる。
作品は『オリバー・ツイスト』『クリスマス・キャロル』『デイヴィッド・コパフィールド』『二都物語』『大いなる遺産』など。
1992年から2003年まで用いられた10UKポンド紙幣に肖像が描かれている。
ディケンズの評価
一般にディケンズの作品は、プロットの巧みさなどにはやや難があり、最良の部分は人物描写などの細部にある、と言われることが多い。多作家でもあるため出来栄えにムラがあるが、『大いなる遺産』などの名作では、そうした描写力に、映画のカメラワークにも似た迫真のストーリー・テリングが加わり、読者をひきつける。精密な観察眼と豊かな想像力で、時代社会の風俗を巧みに描いた。日常生活の描写は具体的で、丹念に細部に亘って生き生きと写し出されており、登場人物の性格はシェイクスピアのそれに比して多種多様であり、ほとんどが典型として戯画化されているにもかかわらず、型を破ってはみ出すような生命力に満ちている。とくに前期の作品においては主人公に個性があまり見られず、脇役にこうした特色を与え作品を盛り上げている。楽天主義と思想主義に支えられた作風
幼少時の貧乏の経験からおのずと労働者階級に同情を寄せ、時に感傷が過度になることもあるが、常に楽天主義と理想主義に支えられ、ことに初期の作品には暖かいユーモアとペーソスが漂っている。その点、ヴィクトリア朝の代表作家として並び称され、中・上級階層を中心に描いたサッカレーとは対照的である。後期には、健康状態の衰えなどの影響もあって徐々に悲観的な価値観に傾斜していき、作品発表のペースも落ちた。
初期の明るいユーモアや天才的なキャラクター造形は目立たなくなっているものの、プロットは複雑で深遠になり、主題を強調することに成功している。
ただし偶然に頼ったご都合主義の物語展開や、最後をめでたく終わるといった典型は最後まで残った。これは月刊分冊という発表形態で、売れ行きや人気を考えてあらすじや登場人物を変えていったためであると評されている。
語句説明
Old Bailey(中央刑事裁判所)カートンやストライバーら法廷弁護士(バリスター)の活躍の場のひとつが、通称「Old Bailey」と呼ばれるCentral Criminal Court(中央刑事裁判所)で、当時ニューゲイト刑務所に隣接(同じ敷地内)していた。
ニューゲイト監獄(Newgate Prison)
スパイ容疑で投獄されているチャールズの弁護をするために、ニューゲート監獄を訪れたルーシー。「ダーネイは絞首刑の後四つ裂きにされるだろう」と聞いて、震え上がる。
ロンドン塔が政治犯や貴族を収容した場所であったのに対し、ニューゲイトは一般の犯罪者を収容した監獄。Old Bailey RoadとNewgate Streetの交わるあたりにあった。
1188年にヘンリー二世の命によって創立されたが、ロンドン大火(1666)で焼失し、1672年に再建、のち1770年に改装される。 はじめはタイバーンで公開処刑が行われていたが、1868年以降は建物の内部で処刑されるようになった。建物は1902年に取り壊される。この時、同敷地内にあった中央刑事裁判所も同時に取り壊され、裁判所だけが再建される。
タイバーン処刑場
ルーシーたちがニューゲートを訪れた時、ちょうどタイバーン行きの馬車も。ニューゲイト監獄からからタイバーン刑場までの道は、ちょうど現在のOxford Streetにあたる道。
タイバーンで最初に絞首刑が行われたのは1571年で、それまではスミスフィールドやタワーヒルで行われていた。この有名な処刑場はハイドパークの北西の角(現在マーブルアーチが立っている場所)にあった。ニューゲイトからタイバーンの処刑場までの4kmほどの道のりHolban, St Giles and Tyburn Road (現在のOxford St.)を、囚人はゆっくりと馬車で運ばれ、沿道には多くの見物客が詰め掛けた。
罪人が人気があった時は、見物人から酒を振る舞われたり、花を投げられたりしたが、嫌われ者は石や汚物を投げつけられたとか。1783年に閉鎖。
Inn
シドニーたちがドーバー海峡近くで泊まったのは「Inn」と呼ばれる宿屋の一種。パブを兼営していることもある。
フランス人嫌い
イギリス人の「フランス人嫌い」ときたら古くからよく知られているが、ここに登場するルーシーの従者ミス・プロスもその典型。 ルーシーを送ってドーバー海峡まで来たときも「フランスなんか死んだって行くものか」と嫌悪感をあらわにする。結局数年後に彼女もフランスに渡ることになるが、その際も"大英帝国の女"としての面目躍如、ルーシーを危機から救う。
フランス貴族たちの亡命
革命の嵐吹き荒れるフランス。イギリスにいたチャールズは「逃亡者」として死刑を求刑される。
フランス革命で財産を没収され、民衆に追われたフランス貴族たちは、この時期イギリスに逃れるものが少なくなかった。バロネス・オルツィ原作の『紅はこべ』もそうした貴族たちを救いだしイギリスに亡命させる手助けをしていた"紅はこべ"ことパーシー・ブレイクニー卿が主人公。
対米戦争の話
チャールズがルーシーにイギリスの対米戦争の話をしていたことが、裁判でとがめられるシーンがある。「ジョージ・ワシントンは将来ジョージ三世より有名になるだろう」と。英国王ジョージ三世は、アメリカ独立戦争当時の国王で、映画『英国万歳!』The Madness of King George(1994) にも描かれているように、晩年は精神を病んでしまう。

