開催内容 桂冠塾【第51回】
『大尉の娘』(プーシキン)
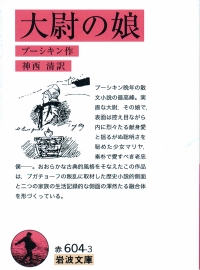
| 開催日時 | 2009年6月21日(日) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 西武池袋線大泉学園駅・徒歩3分 勤労福祉会館・和室(小) |
開催。諸々コメント。
今回はプーシキン作『大尉の娘』を取り上げます。歴史的研究に裏打ちされた小説の分野を切り拓いたプーシキンは、近代ロシア文学における先駆者であり歴史小説の草分け的存在である。
作品の舞台は1700年代後半のロシア。1773~75年に起きたプガチョーフの乱(プガチョフの乱)が大きなモチーフになっている。
主人公はピョートル・アンドレーイチ・グリニョフ。幼名はペトルーシャ。
彼の手記という形で物語が描かれている。
グリニョフは貴族の生まれ。裕福な家系の中で世間も知らずに勝手気ままに育った様子がうかがい知れる。
17歳になり、本来であればペテルブルクの近衛士官になるはずだったが、父の意向で辺境警備の守備隊に入隊することになる。
任地に赴く間にもお坊ちゃんぶりを発揮しながら社会経験を積んでいく。
任地のオレンブルグからさらに転任したベロゴールスク要塞で出会うのがイヴァン・クージミチ大尉の娘であるマリヤ・イヴァーノヴナ。マーシャである。
この要塞で同僚となったシヴァーブリンとマリヤをめぐって死闘を行ったグリチョフは重症を負うが、マリヤとの愛を確かめ結婚を約束する。
充実するかに見えた生活は、突然起こったプガチョーフの乱で一変する。
生死の境目を綱渡りのように、しかし信念を貫いて進むグリチョフ。
そして2年余りの戦乱を経て平定されたプガチョーフの乱の後にグリチョフを待っていたものは...。
作品誕生の背景
1832年末に着想、翌1833年初に起稿し、1836年9月に完成した。同年11月、自身が創刊した文学雑誌『ソーヴリミニク・同時代人』Современник 第4号に発表された。もともとプガチョフの乱に大きな興味を持っていたプーシキンは、『大尉の娘』起稿後、帝国軍書庫での資料検分、反乱が起きた現地(オレンブルクなど)での取材・調査などを丹念に積み重ねた。その成果は、研究論文『プガチョフ史』История Пугачева(1833年完成、皇帝ニコライ1世により『プガチョフ反乱史』に改題)として結実。創作としての『大尉の娘』はそれから3年以上の月日を費やして完成させた。
プガチョフの戦史である『プガチョフ史』に対し『大尉の娘』は、青年貴族の恋と冒険を描いた物語だが、その時代の被支配層の生活や生き方を伝えるものとなっており、ロシアの地とそこに住む人々すべてに関心を寄せていたプーシキンの世界観がよく表れた作品となっている。
本作着想の大きなヒントとなったのは、実際に「プガチョフの乱」においてプガチョフ一派の捕虜となった貴族の士官、ミハイル・シヴァンヴィチ少尉の存在を知ったからだといわれている。捕らえられたシヴァンヴィチは、プガチョフ一派の通訳として働き、反乱平定後はその咎により逮捕されたが、その後は処刑された、女帝エカチェリーナ2世の恩赦があったといくつかの説がある。主人公とシヴァーブリンは、この人物から創造されたキャラクターとされている。
複数の研究者はこの作品には英文学者ウォルター・スコットの影響が見られると指摘している。
主な登場人物
ピョートル・アンドレーイチ・グリニョフ 主人公。17~18歳。シンビルスク(現在のウリヤノフスク)に領地を持つ貴族の子息として、サンクトペテルブルクの近衛士官に任官されるはずだったが、父親が敢えて、辺境の守備隊へ単なる士官として配属させる。階級は少尉補。幼名ペトルーシャ。エメリヤン・イヴァーナヴィチ・プガチョフ ドン川流域に住む豪族(カザーク、いわゆるコサック)、ドンスキーエ・カザーキ(ドン・コサック)出身の脱獄囚。不審死を遂げたとされる皇帝ピョートル3世の名を騙り、ヨーロッパ・ロシア辺境地域で各地のカザークや農民(農奴)、非ロシア人(バシキール人およびキルギス人など)を率いて反乱を起こす。史実では1744年生なので、本作での年齢は30歳程度と推定できる。
マーリヤ・イヴァーナヴナ・ミローナヴァ ロシア帝国軍ベラゴールスク要塞の司令官・ミローナフ大尉の一人娘。年齢は“18歳くらい”と表現される。愛称マーシャ(Маша)。平穏・素朴な生活に育つ。
アルヒープ・サヴェーリイチ グリニョフ家の忠実な家来。年配者。主人公の付添い人としてベラゴールスク要塞に住む。
イヴァーン・クーズィミチ・ミローナフ ロシア帝国軍大尉。貴族ではない叩き上げの士官で、ベラゴールスク要塞の司令官として、要塞守備隊とカザーク部隊を率いる。軍務に忠実な、純朴な人物として描かれる。
ヴァシリーサ・エガローヴナ・ミローナヴァ ミローナフ大尉の妻。軍務には関わらないが、ベラゴールスク要塞の軍人たちを、家族のように仕切っている。20年ほど前に、夫ともにこの要塞に転じてきたという。
アレクセイ・イヴァーヌィチ・シヴァーブリン 士官。貴族出身で元々は近衛士官だったが、5年前に殺人を犯した咎で単なる士官に格下げされ、ベラゴールスク要塞に左遷された。
イヴァーン・イグナーチィチ ロシア帝国軍中尉。ミローナフ大尉の副官。隻眼の年配者で、過去なんども戦争に出征した経歴がある。
マクシイムィチ 伍長。カザーク出身だが、ミローナフ夫妻や士官から信頼されている下士官として描かれる。
パラーシャ ミローナフ家の女中。作中では、親しみをこめたパラーシカ (Палашка) の名で呼ばれることが多い。なお、同名の女中がグリニョフ家にもいるが別人。
ゲラーシム神父 ベラゴールスクの村にあるロシア正教会の神父。
アクリーナ・パンフィーラヴナ ゲラーシム神父の妻。おしゃべり。
アンドレィ・ピョートラヴィチ・グリニョフ 主人公の父親。元軍人。貴族として宮廷に忠誠を誓い続けている。
アヴドーチャ・ヴァシリーエヴナ・グリニョヴァ 主人公の母親
アンドレィ・カールラヴィチ・R ロシア帝国軍将軍。オレンブルク方面軍の総司令官と考えられる。主人公の父親の元同僚で、主人公をベラゴールスク要塞へ配属した。
イヴァーン・イヴァーヌィチ・ズーリン ロシア帝国軍大尉→少佐。驃騎兵連隊所属。主人公がオレンブルクに赴く途中に出会う。
エカチェリーナ2世 ロシア帝国を治める女帝
アーンナ・ヴラスィェヴナ 夏に宮廷が置かれるツァールスコエ・セローの近郊の町・ソフィヤの、馬車駅の駅長の妻
物語の舞台
ベラゴールスク主人公が赴任する“ベラゴールスク要塞”とは、守備隊が駐屯するだけの単なる村であり、城や砦があるわけではない。
この村は架空の集落だが、ヨーロッパ・ロシアのほぼ東端となるウラル山脈西方の都市・オレンブルクからさらに40ヴィルスタ(露里・約43km程度)離れた、ヤイーク川(ウラル川)に近い場所とされる。
18世紀のロシア帝国は、ヤイーク川対岸のカザフ西北部に影響力を及ぼしていたが、国境線はヤイーク川に引いており、物語が舞台とする地域のイメージをはっきり示している。
現在ウラル川は、ロシア連邦とカザフスタン共和国の国境となっている。
プガチョフの乱
ロシアのドン川流域で1773年に発生した大規模な農民の反乱。
コサック出身のエメリヤン・プガチョフが、前皇帝ピョートル3世(女帝エカチェリーナ2世の夫)を僭称して反乱を起こした。一時は数万の軍勢を率いたが、結局は政府軍によって鎮圧され、プガチョフとその仲間は1775年にモスクワで処刑された。
当時の皇帝は啓蒙専制君主として知られるエカチェリーナ2世であり、この反乱を受けて反動的な姿勢を強めることになった。
また、今後こうした反乱が勃発することを恐れたこともあり、統治機構の再編が図られた。
作品の感想
プーシキンは19世紀前半の近代ロシア文学を代表する国民的作家です。本作品は1773~75年に起きたプガチョーフの乱(プガチョフの乱)が大きなモチーフになっている歴史小説の走りとも言え、ロシア文学の研究においても重要な作品となっています。
主人公はピョートル・アンドレーイチ・グリニョフ。
幼名はペトルーシャですが、この一家では男の子の幼名には「ペトルーシャ」の名前が多用されているのでしょうか、彼の孫も「ペトルーシャ」と呼ばれています。
作品は彼の手記という形で孫の「ペトルーシャ」に読ませるために書かれたという体裁が「前詞」で書かれていますが、ロシア国内で発刊される本ではほとんどこの「前詞」は掲載されていないと翻訳者の神西清氏自身によって説明されています。
日本語訳の本のつくりを見ると、神西氏は翻訳家ではなく研究者なのだということを感じます。
「前詞」もそうですが、「拾遺の章」を収めたり、最終稿でプーシキン自身によって削除されている表現がカッコ付きで挿入されています。
また、この作品を表現する文庫本の概略説明等で使われている「生活記録的な側面」という表現も少し特殊です。
この元は、やはり神西氏によるあとがきに書かれている「単なる歴史小説ではなくて、他面に家庭記録の要素を含んで」云々の表現を、そのまま転用したことで生じているのは明白です。
実際に読んでみると、そのような印象はほとんどなく、「生活記録的」というのであれば古今東西の多くの小説作品は同様の表現になるではというのが正直な感想です。要するに要約する出版社の担当者があまり作品本体を読んでいないのかもなぁと感じます。
いずれにしろ、この「生活記録」「家庭記録」という表現は、文学上のカテゴリ分けで行われていることは殆どないと思います。
作品そのものの感想を少し述べておきたいと思います。
この作品の主題はどこになるのでしょうか。
プーシキンの着想は史実であるプガチョフの乱に興味を持ったことですが、モチーフに大きく影響したのはある実在の人物を知ったことだといわれています。
プガチョフ一派に捉えられ通訳として働き、鎮圧後に処刑されたとも、女帝エカチェリーナ2世の恩赦を受けて釈放されたとも言われているミハイル・シヴァンヴィチ少尉がその人物です。
この人物をモデルにして、主人公ピョートル・アンドレーイチ・グリチョフと宿敵シヴァーブリンが生まれたというのが通説となっており、読んでみると「なるほど」と思います。
あまりにも通俗的で自分のためになら信念など、ころころ変えてしまうシヴァーブリン。
富豪の家庭に生まれ、坊ちゃん育ちながら、様々な人生経験を経ながらも、次第に曲げてはいけない信念というものを直感的に体得、実践していくグリチョフ。
シヴァーブリンは「悪」で、グリチョフは「正義」と言ってしまえば簡単な構図になってしまいますが、グリチョフはぎりぎりのところで人生の選択をしていくシーンは読み応えがあります。
ただ、気になる点もいくつかあります。
登場人物の関係をムダなく活かしている点は、ある意味まとまりすぎているという印象が生まれてしまいます。
最終章でのマリヤの行動から生まれる結果は、ペンを急いだのか、少し安直に過ぎる感を感じるのは否めないでしょう。
桂冠塾の参加者からも「漫画(劇画)でありがちなハッピーエンド」「そんなに都合よくいかないよな」という声も出ていました。
そんな印象も含めて、対照的な二人の生き方を通してプーシキンが訴えたかったものは何だったのか。
それは、歴史に埋もれた人間の生き様、信念を貫くという行動の持つ意味を訴えたかったのかもしれません。
プガチョフの乱そのものが前皇帝を詐称したのが発端。
そんな犯罪者かもしれない人物に農民やコサックを中心に数万人が自分達の思いを託した。
この作品からしか推し量ることができないので事実はどうかわからないが、自分達の首謀者は前皇帝ではなくて僭聖者かもしれないと思っていた者も少なからずいたのかもしれないと感じる。
それでも反乱に身を投じた庶民もいたのかもしれない。
何が真実で、何が貫くべき信念なのか。
プーシキンは、私達に、そんな命題を問いかけたかったのかもしれない。
章立て
前詞第一章 近衛の軍曹
第二章 道案内
第三章 要塞
第四章 決闘
第五章 恋
第六章 プガチョーフの乱
第七章 強襲
第八章 招かぬ客
第九章 別離
第十章 町の包囲
第十一章 叛徒の本陣
第十二章 孤児
第十三章 逮捕
第十四章 査問
後詞
拾遺の章
作者
アレクサンドル・セルゲーヴィチ・プーシキン (Александр Сергеевич Пушкин、1799年6月6日〔旧暦5月26日〕 - 1837年2月10日〔旧暦1月29日〕)ロシアの詩人・作家。ロシア近代文学の嚆矢とされる。プーシキンは初めて作品のなかに積極的に口語を取り入れて独自の語りの文体を作り上げ、近代文章語を確立し、後代のロシア文学に影響を与えた。
『大尉の娘』は1833年1月に起筆、1836年10月に脱稿、11月に雑誌「現代人」に無署名で発表された。
父親は由緒ある家柄のロシアの地主貴族、母親の祖父はピョートル大帝に寵愛された黒人奴隷上がりのエリート軍人であった。
モスクワに生まれ、ペテルブルク郊外のツァールスコエ・セロー(現・プーシキン)にあったリツェイ(学習院)での公開試験で朗読した自作の詩がデルジャーヴィンに認められ、その才能はロシアの文学界に広く知られた。
1820年、最初の長編詩『ルスランとリュドミーラ』を発表。
次第に政治色を帯びた詩を発表するようになり、文学的急進派の代弁者となっていく。
それを疎んだ政府は、1820年に彼をキシニョフへ送る。1823年までキシニョフに留まった。
その間、夏にカフカース(コーカサス)とクリミアに旅して長編詩『コーカサスの虜』や『バフチサライの泉』を書き、高い評価を得た。1823年にオデッサに移り住むが再び政府と衝突。1824年に両親の住む北ロシア、プスコフ県ミハイロフスコエ村に送られる。
1826年、皇帝ニコライ1世への嘆願が認められてペテルブルクに戻る。しかし、1825年に起こったデカブリストの蜂起の後の締め付けのために、北ロシアにいた時期に書いた『ボリス・ゴドゥノフ』などの詩を発表することが許されず、政府の監視のもと、窮屈な生活を余儀なくされる。
1831年、ナターリア・ゴンチャロワと結婚。その後、低位の階級を与えられ帝室への出入りを許されるが、この申し出を、美人で、密かに慕う者が多かったと言われる妻ナターリアを帝室に出入りさせるためのものとして、屈辱と受け取った。
1837年1月27日、妻に執拗に言い寄るフランス人のジョルジュ・ダンテスに決闘を挑み、決闘の傷がもとで、その2日後に息を引き取った。政治的騒動を恐れた政府は近親者のみで密かに葬儀を執り行った。
遺体はミハイロフスコエ付近のウスペンスキー大聖堂の墓地に埋葬された。

