開催内容 桂冠塾【第61回】
『罪と罰』(ドストエフスキー)
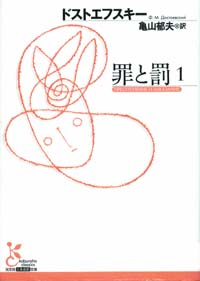
| 開催日時 | 2010年4月24日(土) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 西武池袋線大泉学園駅・徒歩3分 勤労福祉会館 和室(小) |
開催。諸々コメント。
舞台は帝政ロシアの首都・サンクトペテルブルク。主人公は貧困に苦しみながら法律を学ぶ学生ロマノヴィチ・ラスコーリニコフ。彼は故郷に住む年金暮し母と住み込みで働く妹からの僅かな仕送りで学業をつづけていたが窮迫が極まって大学に行けなくなり身の回りのモノを質草に老女アリョーナから金を借りる生活に堕していた。彼の意識はこの老女を制裁することが社会的善であるという方向に急激に傾いていく。
一つの微細な罪悪は百の善行に償われ、選ばれた「非凡人」には社会的道徳を超越する権利があるという論理にとらわれた彼は、老女アリョーナの殺害を計画。多少の逡巡があるがそれらを乗り越えて殺人を実行する。
しかしその場には外出して不在であるはずの老女の妹がいて、その妹までも殺害してしまう。
想定外の殺人を実行してしまったラスコーリニコフは罪の意識に苛まれ、精神の均衡が破壊されていく...。
そんな彼を敏腕の予審判事ポルフィーリーが追い詰めようとする。
娼婦ソーニャの生き方に出会い、犯罪を犯したラスコーリニコフはみずからの人生の決断を下そうとする。ラスコーニコフをはじめ登場する一人ひとりに語りつくせない人生があると感じさせるこの作品のクライマックスは...。
ロシア文学は難しいという先入観をあっさりと拭い去ってくれるのがドストエフスキー作品と言えると思わせるほど、ストーリー展開も素晴らしい作品です。
是非一読をお勧めしたい珠玉の一冊です。
『罪と罰』の時代背景
1850~60年代のペテルブルクの民衆の貧困ロマノフ朝ロシア
▼アレクサンドル1世(在位1801~25年)
→国内改革の着手と侵攻の時代
▼ニコライ1世(在位1825~55年)
→ロシア・トルコ戦争(1828~29年)
→デカブリストの乱(貴族将校の反乱/ロシア社会の開明化、立憲君主制、共和制を要求)
→第三部(秘密警察)による自由主義運動の取り締まり
▼アレクサンドル2世
→1861年 農奴制を廃止(農奴解放令)
→1864年 司法制度の改革
農奴解放
■ロシアにおける農奴制15世紀末にイヴァン3世が農民の移転を制限した法典(1497年法典)を定めると、のちのイヴァン4世も同様の法令を定めた。最終的には、17世紀に成立したロマノフ朝の初期までに、農奴制の立法化が完了した。
歴代皇帝は、ピョートル1世にみられるように、近代化を推進する財源を確保する必要性から(農奴制自体は近代化から逆行するが)農奴制を強化していった。しかし、1856年のクリミア戦争における敗北によって近代化の必要性を痛感したアレクサンドル2世が、1861年に農奴解放令を出したことで農奴制は廃された。
■農奴解放
農奴解放は貴族への多年にわたる「賠償金」とわずかばかりの法律上は認められた人民の自由により危険なくらいに不完全なものであった。人民の権利は、依然として階級ごとに厳格に規定された義務と規則に縛られていた。
農奴解放はロシアが封建的専制政治から市場が支配する資本主義にゆっくりと移行する1860年代に唯一始まった政治・法律・社会・経済の変動である。一連の改革は、経済・社会・文化を構造的に解放したとはいえ、政治体制に変更は見られなかった。改革を試みることは、君主制と官僚制度に厳しく阻害された。例えば40以下の自治体で行うと合意した開発さえ制限され、実施されたのは50年も経ってからであった。
期待が膨らんでも実行過程で制約を受け、結局反乱に発展するような不満を生み出して行った。反乱に加わる人々に「土地と自由」の要求は革命でこそ実現するという考えが生まれた。
革命運動は専らインテリゲンツィアの活動から生まれたと言っても良い。この運動はナロードニキと呼ばれた。この運動は個別に行われたものではなかったが、各々の主張により様々な集団に分かれていった。
初期の革命思想は、貴族のアレクサンドル・ゲルツェンの農奴解放支援とゲルツェンのヨーロッパ社会主義とスラブ的農民集団主義に起源がある。ゲルツェンはロシア社会は依然として産業化が未発達であると言い、革命が起きてもプロレタリアートがいないために革命による変動の基本はナロード(人民)とオブスチナ(農村共同体)であるとする思想に共鳴した。
他の思想家は、ロシアの農村は非常に保守的で、他の誰でもない家族や村、共同体を大切にしていると反論した。こうした思想家は、農民は自分達の土地のことしか考えず、民主主義や西洋の自由主義には深く反対していると考えた。後にロシアの思想は、後の1917年の革命で使われる概念である革命の指導的階級という考えに引き寄せられていった。
司法改革
農奴解放は約4700万人の農民の管理が地主から政府の手に移ったことを意味し、この社会的変化に対応するべく地方自治機関としてゼムストヴォが設置された(ヨーロッパ・ロシア地域のみ)。この機関は地方貴族に地方への影響力を残すと同時に国政参加の機会を与えたが、それでも児童教育・保健事業・貧民救済といった社会の影の部分に目が向けられた。改革は多方面に及び、1864年に断行された司法権の行政権からの独立を始め、国家予算の一本化、徴税請負制度廃止、国立銀行創設といった政府内の構造的近代化・効率化のための施策が矢継ぎ早に行われた。またナショナリズムの要たる国民教育に関しても、ゴロヴニン文部相のもと、1863年の「大学令」で大学を自由化し、翌1864年の「初等国民学校令」「中等学校法」は無償の基礎的公教育を保障した。
後任で保守派の代表格であるドミトリー・トルストイ伯爵も教育改革を熱心に推進し、1871年に女性が教員や公務員となることが許可された。ロシアは女子教育に関しては西欧諸国をはるかに凌いでいた。軍事面での改革は陸相ドミトリー・ミリューチン伯爵の努力に負うところが大きい。ミリューチンは1867年に軍規を大幅に整備し、1874年には全身分の男子に対する徴兵制がしかれた。ただし装備などは西欧列強と較べると、いまだ格段に質が悪かった。
また聖務会院も変革を期待し、ロシア正教会への働きかけを強めた。
ニーコン総主教による改革
ロシア正教会史の中でも特筆される大事件として挙げられることが多い総主教ニーコンによる改革は、特筆されて然るべきさまざまな決定的影響をロシア正教会に残した。この改革に対する評価は賛否両論があり、現代の正教会関係者からも必ずその功罪の両面が挙げられる。彼はアヴァクームらと共に正教会の西欧化に危機感を抱き、正教会の伝統を守る意識を持っていた人物であった。だが1652年にニーコンがツァーリであるアレクセイの支持を受けて総主教に着座し教会の改革を始めた段階で、アヴァクームらの一派と分裂が生じた。
この時代、ロシア正教会では所有派が指導的立場にあったが、所有派は非常に形式を重んじる人々であり、形式主義は非常に深くロシア正教会に根を下ろして居た。
形式主義への偏重を中庸の状態に適正化させる事。
ロシア正教会の形式を、正教世界の中心たるロシアに相応しくギリシャに倣ったものとし、ギリシャの奉神礼・伝統・祈祷書を取り入れることで正教会世界の標準的地位をロシアに確立する事。以てカトリック教会への対抗とする。
これらがニーコン改革によって目指された。
注)
所有派:荒野修道院運動から出発した修道院群により発生した富を積極的に用いて人々を助けるべきだとした人々。
非所有派:隠遁者を多数生み出し、清貧を旨とし財産所有に反対した人々。
ニーコン改革はロシア正教会を革新しようとしたのではなく、あくまで他教会と共通する正教会の伝統を確立しようとしたのみであって、伝統をいかに保持すべきかという問題意識についてはニーコンに賛成した側も、ニーコンに反対する側も、異なるところはなかった。西欧におけるカトリックとプロテスタントの間の相違ほどには両者には見解上の溝はなかったと言える。
だがそれでもニーコンによる改革は、ルーシから先祖代々、祈祷形式を護ってきた自負を持つ人々からの猛烈な反発を生み、反対者から致命者も出た。ツァーリの縁戚からも致命者が出たことにこの反対運動が広く起こっていたことが示されている。これらの改革に反発した人々は「分離派(ラスコーリニキ)」と呼ばれた。古儀式派とも言う。
後代、帝国の安定を期す帝権の思惑から「『分離派』という名称は差別的である」として、彼等に対して若干の配慮が示されるようになり、エカチェリーナ2世の時代から公文書においては「古儀式派」の名称を使用するようになった。現代においても「古儀式派」が、当事者に配慮した名称となっている。
当初は古儀式派に対する弾圧は人頭税を二倍払わせるなどの間接的手段に止まったが、次第に実力行使の面が増大。ニーコン総主教はツァーリの摂政という立場を活かし、古儀式派への実力行使を伴った弾圧を進めていった。古儀式派による集団焼身自殺といった熱狂的な抵抗運動はロシア全国各地でみられた。
主な登場人物
ロジオン・ロマーヌイチ・ラスコーリニコフ (ロージャ) 孤独な主人公。美しいが傲慢な若者。貧困故にヒポコンデリーの症状が強まっている。イニシャル(Р.Р.Р.)を上下反転させると666となる、とされる。ソーフィヤ・セミョーノヴナ・マルメラードワ (ソーネチカ、ソーニャ) マルメラードフの娘。家族を飢餓から救うため、売春婦となった。信心深い高潔な少女。
ポルフィーリ・ペトローヴィチ 予審判事。背が低く肥満体ではあるが、慎重かつ剛胆な能吏。ラスコーリニコフを心理的証拠だけで追い詰め、鬼気迫る論戦を展開する。
アヴドーチャ・ロマーノヴナ・ラスコーリニコワ (ドゥーネチカ、ドゥーニャ) ラスコーリニコフの妹。気高く美しい娘。半ば身売りのような形でルージンと婚約するが……。
アルカージイ・イワーノヴィチ・スヴィドリガイロフ ドゥーニャがもと家庭教師をしていた家の主人。黒い噂が絶えない不誠実な男。ドゥーニャを愛する。物語の冒頭で名前だけ登場し、中盤に突如として現れる。
ドミートリィ・プロコーフィチ・ラズミーヒン ラスコーリニコフの唯一の友達。頑健で痩身長躯の誠実な青年。ドゥーニャに好意を抱く。
セミョーン・ザハールイチ・マルメラードフ 貧乏な元役人。ソーニャの父。生来の浮浪癖と酒癖が祟り、職を失して、愛娘のソーニャを売春婦に貶めてしまう。
カテリーナ・イワーノヴナ・マルメラードワ マルメラードフの2人目の妻。それなりに裕福な家の出。貧困に打ちひしがれ、精神を害している。
ポーリナ・ミハイローヴナ・マルメラードワ (ポーレンカ、ポーリャ) マルメラードフの娘。ソーニャの妹。
アマリヤ・フョードロヴナ・リッペヴェフゼル マルメラードフ一家に部屋を貸している大家。
プリーヘヤ・アレクサンドロブナ・ラスコーリニコワ ラスコーリニコフとドゥーニャの母。
ピョートル・ペトローヴィチ・ルージン ドゥーニャと婚約する弁護士。
アンドレイ・セミョーノヴィチ・レベジャートニコフ ルージンが居候した同居人。ルージンから馬鹿にされている。コミューン思想の社会主義者。
アリョーナ・イワーノヴナ 質屋の強欲な老婆。ラスコーリニコフに殺害され金品を奪われる。
リザヴェータ・イワーノヴナ アリョーナ・イワーノヴナの妹でソーニャの友人。ラスコーリニコフに殺害される。
ゾシーモフ ラズミーヒンの友人で医者。
プラスコーヴィヤ・パーヴロヴナ (パーシェンカ) ラスコーリニコフの長屋の大家。
ナスターシャ・ペトローヴナ (ナスチェンカ) ラスコーリニコフの長屋の召使い。
ニコージム・フォミッチ 区の警察署長。警部。
イリヤ・ペトローヴィチ 癇癪持ちの警察官。
アレクサンドル・グリゴリーウィチ・ザミョートフ 警察署の事務官。ラズミーヒンの友人。
ニコライ 殺害の嫌疑をかけられたペンキ職人。彼の予想外の行動が事件をこじらせる。
作品のあらすじ
物語は6部とエピローグからなり、主に帝政ロシアの首都・サンクトペテルブルクを舞台とする。主人公は、最近大学を退学したラスコーリニコフという青年。
ラスコーリニコフはペテルブルクに暮らしている。
「伝説の英雄のような人類の指導者となるべき選ばれし者は、より大局的な正義を為すためならば、既存の法や規範をも超越する資格を持つ」という独自の理論を持つ青年・ラスコーリニコフは、田舎に暮らす母の年金と妹(ドゥーニャ)の住み込み家庭教師の給金によって学資を出してもらっていたが仕送りが滞るようになって退学を余儀なくされる。ただし彼自身の努力によって回避できる程度であったと物語の途中から推測できる。
彼は、偶然、阿漕な高利貸しの老婆・アリョーナの話を耳にして以来、もし自らにその資格があるのならば、「選ばれし者」として正義の鉄槌を下すべきではないかとの思索を巡らし始め、現状に怒りを抱えた彼自身の理屈から起死回生の資金を得るために金貸しの老女の殺人を計画する。
躊躇するものの様々な偶然(か必然なのか...)が重なり殺人を実行するが、その場に居合わせたアリョーナの妹・リザヴェータも殺してしまい、一気に精神の均衡を失っていく。
母と妹の身の上にも事件が起こっており、結果的に妹はルージンという弁護士と婚約し上京することに。ラスコーリニコフに手紙を送り、再会を果たすが妹の結婚には大反対。ルージンの打算的な下心を直感的に感じとり、ルージンと直接話す中で母と妹もルージンの本心に気づき破談させることに。
善良な老婦人を殺した罪の意識に心を蝕まれはじめたラスコーリニコフは挑発的な行動や異常な行動を繰り返す。その後の彼を待っていたのは、想像を絶する苦悩と葛藤の日々、そして、老姉妹殺害犯を追う敏腕予審判事・ポルフィーリィとの間で繰り広げられる壮絶な心理戦・頭脳戦であった。様々な状況から犯人ではないかと思い始めた予審判事によって追い詰められようとするが、突然「自分が殺人を犯しました」とペンキ職人が名乗り出たことによって事件捜査は終結するかに思われたが、予審判事はラスコーリニコフが真犯人であるという確信を捨ててはいなかった。
そして最後はラスコーリニコフ自身が警察に出頭し自首をして事件は解決することになる。
物語の概要
頭脳明晰ではあるが貧しい元大学生ラスコーリニコフが、「一つの微細な罪悪は百の善行に償われる」「選ばれた非凡人は、新たな世の中の成長のためなら、社会道徳を踏み外す権利を持つ」という独自の犯罪理論をもとに、金貸しの強欲狡猾な老婆を殺害し、奪った金で世の中のために善行をしようと企てるも、殺害の現場に偶然居合わせたその妹まで殺害してしまう。この思いがけぬ殺人に、ラスコーリニコフの罪の意識が増長し、発狂していく。しかし、ラスコーリニコフよりも惨憺たる生活を送る娼婦ソーニャの家族のためにつくす徹底された自己犠牲の生き方に心をうたれ、最後には自首する。人間回復への強烈な願望を訴えたヒューマニズムが描かれた小説である。
一般には、正当化された殺人、貧困に喘ぐ民衆、有神論と無神論の対決などの普遍的かつ哲学的なテーマを扱い、現実と理想との乖離や論理の矛盾・崩壊などを描いた(すなわち、当時広まった社会主義思想への批判でもある)思想小説の類に属するとされる。一方で、老婆殺しの事件を追及する予審判事ポルフィーリィに追いつめられたラスコーリニコフが鬼気迫る勢いで反論する、彼との三度に渡る論戦はさながら推理小説であり、翻訳を手がけた江川卓は『刑事コロンボ』や『古畑任三郎』のような倒叙ミステリーの様相を呈していると語っている。
日本国内では、学生の夏休みの読書感想文を書くための推薦図書として毎年挙げられたり、手塚治虫などによって漫画化されるなど、日本人にもよく親しまれている作品である。
執筆の経緯
ドストエフスキーは、ペテルブルクで兄の遺族の扶養や莫大な借金の返済など、経済的にも精神的にも追いつめられていた。その苦境から脱するため、ある出版社に無謀な契約をして3000ルーブルを前借りし、当座の借金を返済する。そして、1865年7月、国外旅行に出発し、ヴィースバーデンで恋人ポーリナと落ち合うが、そこで残った金を全て賭博で失ってしまう。後には引けない一文無しの状態の中で構想をまとめ、同年10月に友人の協力で帰国。翌1866年1月、雑誌『ロシア報知』にて連載を開始し、同年12月に完結した(同じロシアの文豪トルストイの『戦争と平和』も同時期に連載が始まった)。
ちなみに、ドストエフスキーはこのとき出版社との契約に従い、『罪と罰』の執筆途中に『賭博者』も手掛けた。この『賭博者』は過密なスケジュールの中、速記者のアンナ・スニートキナ(後に2度目の妻となる)の口述筆記により、1866年10月にわずか26日間で書き上げられた。
重要な役割を果たす登場人物
この物語の中で重要な役割を果たすのがソーニャの存在である。ソーニャはマルメラードフの長女。このマルメラードフとは気位の高い妻の性格に押しつぶされ怠惰(と一言でいえない面もある)と酒によって公務員の職を失った男。この家族を養うためにソーニャは公認売春婦として身体を売って生きている。敬虔なキリスト教徒であり、自分自身は救い難い罪を犯し地獄に堕ちることを覚悟、日々他人の目におびえながら生きているような少女であった。
ラスコーリニコフはマルメラードフが馬車に轢かれて死ぬ場面に遭遇し葬儀の費用を出すことになる(このお金はルージンと結婚する前提で得た母と妹から送られたものであった)。
その場で出会ったソーニャに運命的なものを感じたラスコーリニコフ。殺人を犯した彼も人の道を踏み外したと罪の意識に苦しんでいた。罪の意識に苦しみながら神の加護を信じて生きるソーニャの生き方に触れ、彼は自首を決意する。
脇役的な存在として友人のラズミーヒンが登場している。
彼はラスコーリニコフの学友であり、退学後の彼を親身に面倒をみていく。最終的には妹ドゥーニャと結婚する。ラスコーリニコフが殺人者であると疑われた時も彼のことを信じ抜いた。
別の角度で重要な役割を演じるのがスヴィドリガイノフである。
妹ドゥーニャが住み込みで働いていた貴族の主人である。
元々ペテルブルクに住んでいた博打好きの男。もてる男だったのだろう貴族の娘に気に入られて結婚して田舎に暮らしていた。ドゥーニャに好きになり駆け落ちまで画策するが妻に発覚。その後、妻が事故死(彼による殺人が疑われるが真偽は作品の中では判明しないまま)によって得た遺産を持ってペテルブルクにドゥーニャを追いかけて上京してくるが、最後は自殺する。
ドストエフスキーが訴えたかったもの
この作品は様々な問題を投げかけている。何点か指摘すると...
・ドストエフスキーが考える「罪」とは何か
・いったい何が「罰」なのか
・ゲラシム・チフトフ事件が作品に与えた影響
・執筆の動機は何か
・高利貸し商ベック氏殺人事件によって深まった作品のモチーフ
・黙示録の都市ペテルブルク 光と影
・場所の名前 イニシャル表記
・人名と愛称に関わる問題
・ロシアの通貨
・ロシアの大学と学生運動
・当時の現実の学生生活はどうだったのか
・マルメラードフが諳んじる聖書の言葉の意味するもの
・ラスコーリニコフが聞き間違った時間の表現
・信仰面から7月7日の意味するもの
・パレ・ド・クリスタルの出来事の意図するもの
・当時のロシア事情:①裁判制度と警察機構の大改革
・当時のロシア事情:②年金制度
・ラスコーリニコフをとらえた思想:①ナポレオン主義
・ラスコーリニコフをとらえた思想:②終末論
・悪の主人公:スヴィドロリガイリロフの思想的根源は
・スヴィドロリガイリロフとラスコーリニコフとの一致点
・黄の鑑札とは何か
・カペルナウーモフ家の象徴
・ソーニャの聖書が意味するもの
・「踏み越えた」のは誰か、何か。
・棺を想起させるラスコーリニコフの部屋とソーニャの部屋
・死者として位置づけられた者たち
・「ラザロの復活」を読ませることによって意図したこととは
・「4」の意味
・「神を見るお方」とはどういう意味か。
・レベジャートニコフの「コニューン」思想
・フーリエ主義とは
・ポルフィーリーはいかなる人物か
・カテリーナの歌う流行歌
・ミコールカと「逃亡派」
・父称の問題(イワンとピョートル):ドストエフスキーの意図
・名前の混合は意図的か
・スヴィドロリガイリロフの「棺」の意味するもの
・人工的都市ペテルブルクの地理的環境:ネヴァ川と天候の問題
・副署長(火薬中尉)の役割
・リヴィングストンの手記とは何か
・ラスコーリニコフの「刑罰」の重さと意味合い
・旋毛虫の夢が意図するものとは
・ドフトエフスキーにとっての『罪と罰』の意味とは
・犯罪と犯罪者への傾斜
・妻マリアとの愛の終わり
・運命の女アポリナーリヤとの出会い
・どん底で誕生した『罪と罰』
・ペテルブルクの暑い夏
などが列挙される。
ドストエフスキー作品は論理的構築がしっかりしており、後世の研究者にとっては研究しがいがある作品群である。実際、多くの研究者がドストエフスキー作品、そして彼自身に関する研究書を出している。上記の指摘もそうした研究書に沿うものである。
彼の執筆の直接的な動機が、ギャンブルによる借金を返済するという切羽詰った状況によることを考えると、よくぞここまで綿密なプロット構築と心理描写ができるものだと感服してしまう。当時の社会状況、政治の施策についての批判も論理的に展開もしている。
その中でも特に、心理描写は群を抜いている。
登場人物の本心がどこにあるのか。またおそらくその人物自身が自分の気持ちそのものがよくわからない、その心理状態までも実に克明に再現している。読んでいて読者である私たちが「どきどき」してしまい、登場人物と同様に不安定な想いにまでさせられていく感覚は不思議としか表現できないような...ある意味で未体験の感覚であった。
「罪」とは何か「罰」はどんな意味があるのか
一点だけ指摘、また語り合いたいと思うのはドストエフスキーがこの作品で言わんとした「罪」とは何か、「罰」とは何か、ということです。安易に結論を出すのではなく、また色々な人の立場に我が身を置いて思索することも大切だと思います。
そして、その「罪」と「罰」の認識は適切なものなのか?
今一度、私たちが思索しなければならないのではないかと感じています。
作品の「エピローグ」はある意味で牧歌的である。 ハッピーエンドと表現してもよいと思う最終章の最終段落は次の言葉で締めくくられている。
しかし、もう新しい物語ははじまっている。
ひとりの人間が少しずつ更正していく物語、
その人間がしだいに生まれかわり、
ひとつの世界からほかの世界へと少しずつ移りかわり、
これまでまったく知られることになかった現実を知る物語である。
これはこれで、新しい物語の主題となるかもしれない---
しかし、わたしたちのこの物語は、これでおしまいだ。
(亀山郁夫訳)
ひとりの人間が少しずつ更正していく物語、
その人間がしだいに生まれかわり、
ひとつの世界からほかの世界へと少しずつ移りかわり、
これまでまったく知られることになかった現実を知る物語である。
これはこれで、新しい物語の主題となるかもしれない---
しかし、わたしたちのこの物語は、これでおしまいだ。
(亀山郁夫訳)
ドストエフスキーは『罪と罰』を通して、人間の可能性を最後まで信じ抜く大切さを訴えたかったのかもしれない。
作者
フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキー (:Фёдор Михайлович Достоевский)1821年11月11日(ユリウス暦10月30日)~1881年2月9日(ユリウス暦1月28日)。レフ・トルストイやアントン・チェーホフとともに19世紀後半のロシア文学を代表する小説家、思想家。
当時広まっていた理性万能主義(社会主義)思想に影響を受けた知識階級(インテリ)の暴力的な革命を否定し、キリスト教、殊に正教に基づく魂の救済を訴えた。実存主義の先駆者とも評される。
モスクワの貧民救済病院の医師の次男に誕生。15歳まで生家で暮らす。16歳の時に母、18歳の時に父を亡くす。17歳で中央工学校に入学し卒業後に工兵局に勤務するが翌年2月に退職し執筆に専念。1845年5月に『貧しき人々』を発表、批評家ベリンスキーに「第二のゴーゴリ」と激賞され華々しく作家デビューするが、その後発表した作品は酷評された。ペトラシェフスキーが主宰するフーリエ主義(空想的社会主義)サークルのサークル員となり、1849年に逮捕されペトロパヴロフスク要塞監獄に収監。死刑判決を受けるが執行直前に恩赦になり1854年までシベリア流刑地で服役する。シベリア守備大隊に勤務、マリアと結婚し1858年にペテルブルクに帰還。この間に理想主義者的な社会主義からキリスト教的人道主義者へと思想的変化があったとされる。
『死の家の記録』『虐げられた人々』『地下室の手記』『罪と罰』を発表し、社会的にも再評価された。
ドスエフスキー自身の賭博好き、持病のてんかんが創作に強い影響を与えたとされる。賭博の借金返済のため悪徳出版業者ステロフスキーと契約をし、全作品の著作権の譲渡、4ヶ月以内の新しい長編小説を書き上げるという条件で3000ルーブルを前借した。借金を完済したドストエフスキーは残金を持ってヨーロッパ旅行に出るが、最初に訪れたヴィスバーデンでルーレットで有り金を使い果たす。
そんな1865年9月、当地で『罪と罰』の執筆が始まった。10月、コペンハーゲン経由でロシアに帰国し執筆が続けられ、12月22日に最終稿に至った。翌1866年『ロシア報知』1月号から連載が開始されると一気に人気小説となった。4月4日に起こった皇帝襲撃事件に影響を受けながら12月号で完結した。ステロフスキーとの契約によってもう長編一本を11月1日までに仕上げる必要から『罪と罰』のエピローグと『賭博者』は口述筆記(速記)によって執筆された。この間に愛が芽生え、速記係アンナ・スニートキナは1867年にドストエフスキーの2番目の妻となる。
小説以外の著作として『作家の日記』がある。雑誌『市民』で担当した文芸欄(のちに個人雑誌として独立)であり、文芸時評、政治社会評論、エッセイ、短編小説、講演原稿(プーシキン論)、宗教論(熱狂的なロシアメシアニズム)を含み、ドストエフスキー研究の貴重な文献となる。
晩年1880年に集大成の『カラマーゾフの兄弟』を脱稿。1881年1月28日に家族に看取られ60歳で逝去。残した著作は35篇で、短編も少なからず残されている。

