開催内容 桂冠塾【第63回】
『峠』(司馬遼太郎)
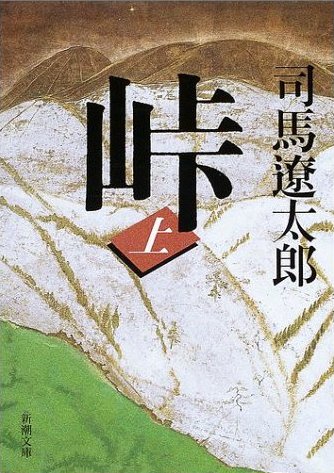
| 開催日時 | 2010年6月26日(土) 14:00~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 西武池袋線大泉学園駅・徒歩3分 勤労福祉会館 和室(小) |
開催。諸々コメント。
今回の本は幕末の越後長岡藩を舞台にした歴史小説です。主人公は河井継之助。下級武士の彼が家老に抜擢され、幕末史上最も熾烈とされる北越戦争に長岡藩を突入させていくことになる。
『峠』は毎日新聞の新聞小説として1年半掲載され、終了と同時に『坂の上の雲』の連載が開始。文学的評価、国民的な人気共に圧倒的に『坂の上の雲』が高いが、その作品に繋がる淵源が『峠』にあるとの指摘がある。河井継之助の歴史評価には賛否両論があり、司馬・継之助の人物観に対しては歴史誤認との批判もある。
在国の時から陽明学を学び、改革派としての資質を育てていた継之助は、自ら談判をして江戸出府の許可を得て江戸に向かう。嘉永5年(1852年)秋、25歳の時である。斎藤拙堂、佐久間象山の塾に通い、歴史や世界の情勢を学ぶ。ペリー来航に際して藩から広く求められた意見提出で藩の目に留まった継之助は、御目付格評定方随役に任命され帰藩するが、旧態依然の体質に拒まれ活躍の場を得ることはできない。
その後2度目の遊学に出た継之助は江戸、備中松山、長崎、横浜を遊歴し帰藩。この後藩主牧野忠恭と共に京都詰、老中公用人と活躍を始める。
郡奉行に任じられた継之助は藩政改革に着手し成功させる。
これが後年の歴史に残る越後長岡藩の慶応改革である。
その後時代は急転回する。慶応3年に徳川慶喜によって大政奉還が行われると討幕派は王政復古を主張し対立。継之助は上洛して公武斡旋を試みるが甲斐なく戊辰戦争に突入する。旧幕府軍として忠義を誓い戦うものの、旧幕府軍は敗退し慶喜も江戸に逃れるに至って、継之助は藩主を帰藩させ、江戸屋敷の家財を売却し、暴落した米の売買で軍資金を確保、ガトリング砲などの近代兵器を買込んで長岡に帰藩する。
そして一藩武装中立を主張し新政府との交渉に臨むが...。
近い将来、士農工商の身分はなくなると見通していた河井継之助。聡明な開明論者であった継之助が長岡藩士として生きねばならなかった幕末の時代。同時代を、同様の見識を有して活躍した勝海舟や数々の英雄に比して、彼の生き先には多くの制約が横たわっていたのも事実である。
そうした中で河井継之助がとった行動とはいかなるものだったのか。いま混迷の度合いを深め、信じるに足る人物がいなくなった感すらある現代を生きる私たちが学ぶべきものがあるように思えてならない。
少し長い作品ですが、今一度共々に読んでみたい一書です。
『一藩武装中立』
時代は幕末。舞台は現在の新潟県長岡市、越後長岡藩。主人公は河井継之助である。
継之助が目指していたのは『一藩武装中立』。諸藩が新政府・旧幕府に分かれて争うなか、他力に頼らず、冒されず、己の力で生きていくことを志向したがその考えは理解されず、開戦へと突き進み、戦いのなかで落命していく。
安政5年 長岡
物語は安政5年の長岡から始まる。一度目の遊学から帰藩し、再度の江戸遊学を主席家老・稲垣平助に直談判する場面からである。
継之助は24歳で7つ年下のすがを妻に迎えるが、近い将来長岡藩の執政になるとの自覚から26歳で単身江戸に遊学。斎藤拙堂、佐久間象山らの門を叩く。
黒船が来航し事態の容易でないことを肌で感じた継之助は、藩主・牧野忠雅(ただまさ)に藩政改革の必要性を建言。これが採用されて帰藩、評定方随役を任命されるが彼の活躍する場面はなく、まもなく退役。
安政4年(1857)父から家督を引継ぎ、外様吟味役に起用されるが、藩政改革の思いがやみがたく。
安政5年(1858)に再び継之助は峠を越えて江戸へ。横浜の守備役に問題を起こすが切り抜けた後は西へ向かう。津の斎藤拙堂と再会し京都を経て目指したのは備中松山藩(岡山県高梁市)の陽明学者山田方谷(ほうこく)の門。
継之助は藩の危機的財政を救った改革者の門で半年間を暮らしたあと世界の動向を察したいと長崎に入る。
万延元年(1860)34歳で帰藩。
動乱の中で藩政改革。軍備増強へ。
尊皇攘夷運動が激化する中、藩主の牧野忠恭(ただゆき)に京都所司代、さらに老中職の依命が下る。継之助は幕府もろとも失墜しかねないと辞任を求めたために忠恭は機嫌を損ね、継之助は辞職をしてこれを償うことになる。
慶応元年(1865年)忠恭の抜擢で再び外様吟味役に就任すると案件だった山中村(現在の柏崎市)の庄屋と村民の争い(山中騒動)を解決しこれを布石に異例の昇進を遂げていく。
この間継之助は藩の組織・財政改革をはじめ、慣習化した賄賂や賭博、遊郭も廃止させた。
武士の不当な取り立てを罰して農民を救い、商業発展のため、川税や株の特権を解消。藩士の禄高是正や門閥解体も当時、画期的なものであり、継之助は端倪すべからざる手腕をいかんなく発揮していく。
継之助は、封建社会の古びた秩序を一掃し、人心の刷新を図ろうとした。夢に描いたのは新鋭な国家構想ー他力に頼らず、冒されず、己の力で生きていく「武装中立国」の実現。
そのために軍備に極めて力を入れ、「ミニエー銃」、初の機関銃「ガトリンク砲」まで武器商人スネルから購入していく。そして中島村に兵学所を整備してフランス式兵制を推進し、長岡藩は雄藩に劣らない近代武装化を急速に成し遂げていく。
大政奉還。北陸戦争へ。
慶応3年(1867年)10月に幕府より朝廷に大政奉還、12月に「王政復古の大号令」が発せられ、新政権を掌握した討幕派らにより旧幕府派の排除が開始された。翌慶応4年1月3日「鳥羽・伏見の戦い」で旧幕府軍と新政府軍が激突し戊辰戦争が開戦。新政府軍は江戸城を無血開城させるなど戦況を有利に進めると並行して、東国に点在する旧幕府派の反抗勢力を制圧するために各地に軍を送る。
越後には3月15日に高田(現在の上越市)に北陸鎮撫総督らが到着し、越後11藩に対して軍資金と兵士の供出を求めた。
継之助はこれに対し沈黙を守る一方、幕府派である奥羽越列藩同盟からの加盟要請を断り、中立の姿勢をとる。
諸藩のほとんどが新政府軍に恭順する中、4月19日に北陸道参謀・山縣有朋、黒田清隆が高田に入る。中立の立場をとる長岡藩に向け進軍が開始され、4月27日に新政府軍は小千谷を占領。この日継之助は軍事総督に任命される。
5月2日小千谷会談に臨む。慈眼寺で継之助と会談したのは山縣や黒田ではなく、当時24歳の岩村精一郎。新政府軍は直前の会津藩等との戦闘で長岡藩が旧幕府軍に加担していると思い込み態度を硬化させる。
継之助は戦闘の意思がないことを訴え、幕府軍説得のための猶予を願い出るが、岩村がこれを一蹴し一方的に会談を決裂させたためやむなく継之助は徹底抗戦のみが残された道と決断する。
長岡藩は奥羽越列藩同盟に正式加盟し、幕府軍の一員として敗北の道を転がり落ちて行く。
当初の継之助の理想は消え去り、長岡は北越戦争最大の激戦地の運命を辿っていった。
新政府軍との激突。波乱の生涯に幕。
新政府軍約2万人の軍勢に対して同盟軍は5千人。継之助は長岡の南の要衝、榎峠の奪還作戦を画策し5月10日に開戦。同盟軍は榎峠の奪取に成功し、続く朝日山の獲得にも成功。
二度の惨敗に新政府軍は作戦を変更。新政府軍は5月19日、濁流で長岡藩が油断した信濃川を渡り守備が手薄かつ守勢に不利な長岡城下に迫る。
継之助自らガトリンク砲を操縦して対抗するがあえなく長岡城は落城した。
継之助は長岡城奪還作戦を意図し決行する。陽動と奇襲作戦で6月25日未明に長岡城の奪還に成功。
しかし長岡軍の勝利は一時的でしかないことは当初から自明であり、ついに新町口での戦いで総指揮官である継之助が左足に銃撃を受けて重傷を負ってしまう。
総指揮官の負傷と交戦の疲労、に加えて新発田藩の寝返りで戦況は悪化の一途をたどり、奪還よりわずか4日後の7月29日長岡城は再び落城した。
城を失い重傷を負った継之助は会津領へと逃げ延びていく。
しかし継之助の容態は悪化。継之助は自らの火葬の指示を出した直後、1868年(慶応4年)8月16日午後8時頃、会津領塩沢村(福島県只見町)にて42年間の波乱の生涯に幕を下ろした。
後日譚
継之助亡き後、同盟諸藩は次々と脱落、流浪の身となった長岡藩は1868年(明治元年)9月23日無念のうちに降伏を告げた。3ヶ月に及ぶ激戦の結果、長岡の街は焼き尽くされ、戦死者は300名余におよび、100名近い領民が犠牲になった。その後長岡藩は「賊軍」と蔑まれ辛い歴史を歩む。禄高は7万4千石から2万4千石に減封、人々は困窮するが「質実剛健」を誇る長岡人は残る力を振り絞り長岡を復興させ力強く歩んでいく。
本作品を執筆した意図
庶民からの人望があり、行政の実務能力も高く、将来を見通す力もある。新しい技術や革新的な考えを受け入れる素養もあって、武力と統率力も兼ね備えていた。そんな河井継之助が、どうして新しい明治の時代を生きることができなかったのだろうか。
司馬遼太郎は「あとがき」で本作品を執筆した意図を次のように書いている。
私はこの「峠」において、侍とはなにかということを考えてみたかった。
それを考えることが目的で書いた。
その典型を越後長岡藩の非門閥家老河井継之助にもとめたことは、書き終えてからもまちがっていなかったとひそかに自負している。
これが本作品のテーマであることは間違いないであろう。それを考えることが目的で書いた。
その典型を越後長岡藩の非門閥家老河井継之助にもとめたことは、書き終えてからもまちがっていなかったとひそかに自負している。
また司馬氏はその直前で、幕末人を生み出した二つの要素として
1.人はどう行動すれば美しいかと考える江戸の武士道倫理
2.人はどう思考し行動すれば公益のためになるかという江戸期の儒教
をあげ、 幕末期に完成した武士という人間像はその結晶のみごとさにおいて人間の芸術といえると語っている。
私は司馬氏の展開する武士観に反駁するつもりは毛頭ないが、ただ、河井継之助の選んだ道が果たして「人間の芸術」というにふさわしい生き方であったのか、その点については甚だ疑問を感じざるをえない。
司馬氏は継之助を評して、一国の宰相にもなれるほどの技量と時代を見抜く先見性があるなど絶賛しているが、はたしてそうであろうか。
元々人間たるもの、何を目的に人生の進むべき道を決めるべきであろうか。
河井継之助は何よりも優先して「長岡藩の藩士」、「牧野家の家臣」であることを絶対条件として、全ての思考と行動の規範としていた。そもそもこの出発点に間違いはなかったのだろうか。
肯定できるか?河井継之助の生き方
継之助の判断基準とは、あえて現代を生きる私達の立場に置き換えてみれば、次のような感じだ。日本人や一個の人間として思考するのではなく、更に限定された自分が属している集団、具体的にいえば勤務している会社の一員として、人生全ての日常行動を規定するということになろう。
継之助的に言えば、早かれ晩かれその会社は倒産の憂き目にあうのは必定であり、国家としても新しい社会システムの導入を進めていて、そのシステムで会社を再編することができるから賛同して協力せよと政府から言われているような状況である。
そんな状況下で「いえいえ私たちは日本国家としての新しいシステムは認めるが、それを自分の会社そのものを国家としてやるから日本国に属さない自治権を認めてくれ」といっているようなものである。
そういいながら新しい国家政府に反抗する旧体制勢力と仲良く情報交換しているような印象をもたれている...。
ざっくり、そんな感じだといえないだろうか。
一人の人間として、ではなく、会社人として全てを判断する。
これが必ずしも正しい判断を生まないことは、多くの人にとって自明の理ではないだろうか。河井継之助の行動は必然的に矛盾を生み出すと私は受け止めている。
その結果、何がもたらされたのか。
長岡藩としての決断に何ら関係していない庶民、領民の多くが戦闘に巻き込まれて生命を失っていった。彼らはなぜ死ななければならなかったのであろうか。
完全な無駄死である。
その死は河井継之助の決断によって必然的にもたらされた結果である。
この一点だけから結論付けても、継之助の行動は誤っていたのである。
ブレのない決断をするために必要なものとは
では河井継之助は、そしてあの時代の指導者はどのように決断し、行動すべきだったのだろうか。歴史には「たら」「れば」はあり得ないし、一様に「こうすべきだった」というような荒っぽい結論を断じるつもりはない。ただ原理原則はいつの時代でも同様ではないかと私は思う。
それは、
・特定の人だけではなく、もれなく自他共の幸福を目指す社会
・懸命に生きる名もなき庶民が安心して暮らせる社会
・他人の不幸の上に自分だけの幸福を築くような社会にしない
という実直な表現に集約される社会構築を目指すことで、ブレのない決断ができると私は考えている。さらにこうした考えは「生命尊厳」という言葉で集約されると私は思う。
こうした視点で再度作品中の河井継之助の言動を見てみると、重要な局面でのブレた行動や言動の不足があることが見えてくる。
いくつか指摘すると
・元々の目的(主君牧野家の温存)自体が誤っていた。
・牧野家温存と一藩独立とをつなぐ論理性が明確でなかった。
・越後長岡藩としての「一藩独立」の主張を語る前に兵器による武装化を進めた。
・自説を関係者に納得させるという対話の努力を全く行なわなかった。
・江戸から引き揚げる際に会津藩など旧幕府軍の藩士を船に同乗させた。
・小千谷会談で新政府軍側に理解してもらうための事前準備を全く行なっていない。
・自分の考えは正しいから回りの人間は理解できなくてもただついてくればいいと思っていた。
・小千谷会談が決裂した時点で投降せず徹底抗戦する道を選ぶ基準が当初目的(牧野家の温存)からずれていった。
等などである...。
冷静にこの物語の流れを俯瞰すると、河井継之助がめざす目的(その妥当性は置いておくとして)を達成する方策は「一藩武装中立」だけではなかったということがわかる。
一藩武装中立はいくつかの有力と思われる方策のひとつにしか過ぎず、環境条件や状況の変化を勘案して、柔軟に取捨選択すべき方策のひとつに過ぎなかった。
しかし継之助は、そうした他の方策の可能性を検証した形跡は、ない。少なくとも『峠』に書かれている文章には何ら表れてきていない。
河井継之助の決定的な過ち-師弟観の欠落-
そしてもうひとつ指摘しておきたいのは、河井継之助は人を育てようとしていなかった点である。仮に継之助の努力が実を結び、薩長中心の新政府勢力と旧幕府勢力と距離を置きつつ軍備増強によって武装中立を勝ち取ることができたとしよう。
そのあとはどうする積りだったのだろうか。せいぜい書かれているのは、藩をあげて商売をするという程度である。それで果たして独立国家としての運営ができたのだろうか。
本当に継之助が独自の理想を抱いて国家建設を行なう積りがあったならば、何を差し置いても人を育てるべきだと気づくと私は思う。
しかし河井継之助の人生には人を育てた形跡が残っていないのだ。
ニーチェの言葉に「無私の意向でなにか偉大なものの基礎をきずいた人は、自分の後継者を養成しようと心掛ける」とある。
一人の人間ができることにはおのずから限界がある。
時代を超えて、一個の人間の限界を超えて偉業を成し遂げるためには、世代を超えた理念信念の継承が不可欠であることは古今東西の歴史が証明済みである。
継之助と同時代を駆け抜けた偉人達の多くは、人を育てることの重要性を認識していた。勝海舟しかり、吉田松陰しかりである。
吉田松陰が開いた松下村塾の出身者が、幕末から明治にかけての日本の夜明けを強力に牽引した事実は多くの日本人が認めるところだ。
吉田松陰と河井継之助。
そのいずれの生き方が多くの庶民に貢献できたのか。
両者の思想的な価値は、具体的な行動として「人を育てる」という行為の有無で明暗をわけたといえないだろうか。
その視点から再評価すると、時代を超えた理念信念の継承を拒絶した河井継之助の生き方は自らの栄華を欲した権力者の姿に過ぎないとも言える。
それは後継者を育てなかっただけではなく、継之助自身が師匠を求めなかった生き方としても現れていると私は思う。
師弟観の不在。
それが継之助の資質の決定的欠落であり、結果として師匠を求めず後継者を育てなかった。その行き着く先は必然的に狭隘にならざるを得ず、時代を超えた偉業など思い描くことすらできなかったのだと私は感じている。
結論的に言えばしょせんは「一国の宰相」の器などではなく、目先の効く実務担当者に過ぎなかったともいえる。
もし仮に司馬遼太郎氏が言うように、継之助が本当に「美しく生きるか」を追求していたのであれば、中途半端な我見や体裁など振り捨てて、先哲に学び、後継の人材を育てたと私は思う。
また私自身が同じ立場であればそうすると思う。
しかし継之助はそうしなかった。
それが彼自身の生き方の限界なのではなかろうか。
哲学不在の生き方からの脱却 師弟観の必然性
河井継之助の生き方を通して「武士の美学」を語るのは、あまりにも荒っぽすぎないか。少なくとも私はそう感じている。もし継之助の生き方が武士の美学の完成形と言うのであれば、武士の思考とはあまりにも短絡的で、哲学思想的にも浅薄であり、自己破壊的だ。そんなものではあってほしくないと思いたい気持ちもある。
河井継之助の行動の失敗は、哲学理念の不在に、その根本原因があった。
自身の信念を疑わず、師匠を持つことをせず、後継の人材も育てなかった。
それが判断基準の誤りに直面しても誰からも指摘を受けることができず、自身が行き詰ったときにその思いを託することすらできなかった。
師匠も後継者も求めないという師弟観の不在が、継之助の生き方を刹那的にせざるを得なかったのではなかろうか。
そして継之助は、長岡藩士、牧野家家臣である自分自身だけを全ての行動の規範においたがゆえに、長岡藩の存続が消え去ろうとしたときに、思考停止に陥った。
ゆえに、牧野家の血筋を繋ぐためにフランスへ亡命させる手はずがついたあとの継之助の行動は持続性のない、刹那的に堕していったのであろう。
それは継之助の哲学理念の不在が成せる業であったことは間違いないと、私は思うのである。
未来へ。希望ある社会に。
振り返って、現代を生きる私達はどうだろうか。哲学信念、師弟観。
いずれも、あきらかに避けて通ろうという風潮がスタンダードになっている現代である。
無意識のうちに自分自身の行動規範を小さく狭めて、自ら思考停止に入り込もうとしていないだろうか。ある面、信念だとか師弟だとかを軽く嘲るように振舞うほうが、楽にかつスマートに生きているように受け止められるのも事実である。
しかし、あえて一歩踏み込んで苦労する人生を選ぶのも、自分自身の決断である。
混迷する現代にあって、確固たる哲学理念と師弟観を求めることがより積極的な生き方であり、それを貫こうとするのも、自分自身で決めることができる人生の醍醐味であると私は思うのである。
長岡藩と戊辰戦争・略年表
1867年(慶応3年)■10月 大政奉還
1868年(慶応4年)
■1月3日 鳥羽・伏見の戦い。戊辰戦争勃発
■3月3日 江戸藩邸を整理。ガトリング砲、小銃等を購入
■4月26日 継之助、軍事総督に就任
■5月2日 新政府軍と交渉。しかし小千谷会談は30分で決裂
■5月3日 長岡藩、開戦決定。奥羽列藩同盟に加盟
■5月10日 榎峠の合戦。新政府軍との戦闘を開始
■5月19日 長岡城落城
■7月25日 長岡城奪還。継之助、銃撃され重傷
■7月29日 長岡城再び落城。長岡軍は会津領へと敗走
■8月16日 継之助、会津塩沢で没する。42歳
1868年(明治元年)
■9月23日 長岡藩主・牧野忠訓、米沢で降伏
1869年(明治2年)
■5月18日 榎本武揚・降伏。戊辰戦争終結
常在戦場
越後長岡藩7万4千石の藩主は三河国牛久保(愛知県豊川市)の土豪から身を興した牧野氏で、元和4年(1918年)に譜代大名として長岡の地に入封した。藩に伝わる「牛久保の壁書」は、牧野家が戦乱の地で培った武士の心得、18条をまとめたもの。250年間の統治によって深く長岡の地に浸透し、今日に至るまで影響を与える。中でも「常在戦場」の4文字は、かつて藩士たちの一番の信条。
継之助もこの言葉を愛した。

