開催内容 桂冠塾【第157回】
『おごそかな渇き』山本周五郎
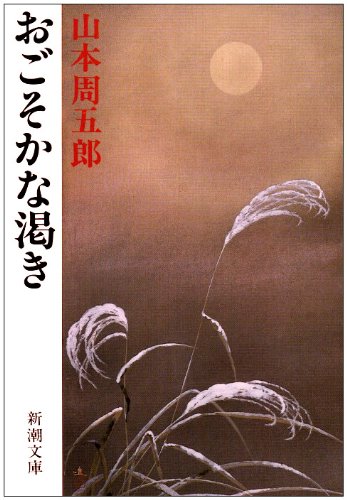
| 開催日時 | 2024年2月24日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 開催方法 | オンライン開催 |
開催。諸々コメント。
山本周五郎氏が長年思索し続けてきた宗教観を集大成しようと取り組んだ一書。完成まで至らず絶筆、遺作となった。宗教的課題を取り上げて「現代の聖書」たらんとした意気込みに対して、残された文章はあまりにも短い。
周五郎氏は何を思い、何を解き明かそうとしたのか。
わずかであれその思いに迫ってみたいと思います。
作者
山本周五郎(1903~1967)本名:清水三十六(さとむ)1903年(明治36年)6月22日、山梨県北都留郡初狩村(現:大月市初狩町下初狩)で生まれる。
日本の大衆文学の第一人者。当時、一段低く見られていた大衆文学を開花させ純文学との垣根を取り払った功績は大きい。
学歴なき作家の代表格でもあり、各種の文学賞をことごとく辞退した無冠の作家。
代表作に『樅の木は残った』『長い坂』『赤ひげ診療譚』『青べか物語』『さぶ』など多数。
1967年(昭和42年)2月14日7時10分、仕事場であった旅館「間門園」別棟で肝炎と心臓衰弱のため死去。
章立て
祝宴初めに飢があった 一~七
川には魚がいた 一・二(絶筆)
あらすじ
祝宴終戦から16年。村長・島田幾造の屋敷で男子出生の祝宴をしている。 宗教の盛んな土地柄で真宗(浄土真宗)と禅宗の家系間では反目と敵意が続いていた。
島田家は永平寺(曹洞宗・禅宗)の信者だが村人は真言宗と一向宗がほとんど。冠婚葬祭には宗旨の同じ者しか集わない。この祝宴にも12,3人しか列席していなかった。
村長の家系は隠れキリシタンだと隣の男と話す竹中啓吉。
福井県大野郡山品村。涸沢を挟んだ谷合で細長い田畑と段々畑と棚田の貧困農村。木炭、川魚の焼干し、茅萱、わずかな繭で生活してきたが、暮らしの近代化で村は莫大な借金を背負っていた。
村長は岩屋の水をミネラルウォーターとして販売して村を豊かにすると言う。
油屋の親方が座る。上座に座っていた竹中は問われて無宗旨と答える。
家の女中が入ってきて行き倒れ人がいると告げる。
初めに飢があった
一
行き倒れの松山隆二。空腹を感じなくなっている。度の違う眼鏡をかけているような気持ち。餓死する時はこんな感じか。
倒れる直前の回顧。高川の叔父、松山船長、中島漁労長、いい人ばかりだった。
これで死ぬのかなと思った。人間のすることには限度があると思う。本当にそうだろうか、とも。
二
松山隆二の様子を見た竹中啓吉は14歳の娘のりつ子に医者を連れてくるように告げる。
「ホワットエバー・ゴッズ・メイビイ」とうわごとを言う松山隆二。クリスチャンか多神教徒かと話す村田医師と竹中。
すいとんを持ってきたりつ子を村田医師がひやかす。娘は性的な本能が働き出す11,12歳頃が一番危ないと言う。
竹中は村田医師に自分の来し方を話し出す。
5年前に女房を亡くし東京が嫌になりこの土地にやってきて少しの畑や薪、炭づくりを作っている。夜具も一つで娘と一緒に寝ていて下腹部を擦り付けられて困惑したこともある。
それが自然だと村田医師は言う。娘はその後多くは男なぞ見向きもしなくなるがごく稀に泥沼に入り込む者もいる。年頃の子供から危ない条件を取り除こうとすると何も残らない。
「神は人間に命を与え、それを奪いたもう」と村田医師は言う。
松山隆二は世話をしてくれるりつ子に身の上を尋ねる。
ここは山品村、父は竹中啓吉で5年前に東京から来た。母は東京の時にいなくなった。事情はわからないが下宿の中川さんもいなくなった。父は何度も東京は人間の住むところではないと言った。下の吉野村にしるべがありこの小屋に越してきた。兄がいたが3歳で死んで記憶にない。遠路のため学校には行かず父に習っている。父は中学校の教師だった。
松山隆二は東京に行くと答える。
三
松山隆二は5日目に起きられた。竹中啓吉は山で炭を焼いている。問われてりつ子が話す。
一人の留守番は慣れた、友達はいない、意地悪をされたことはあるが自分はしない。
松山隆二は考える。人の心に芽生える憎悪や敵意にも意味がある、サタンがヨブの信仰心を確かめたように。
翌日二人で山に向かう。鳥の鳴き声を聞き分けるりつ子は同級生だったきよの話をし、松山隆二は鳥の鳴き声が人の怒りをかきたてることに思いを巡らしブラウン運動を想起する。善と悪、是と非、愛と憎しみ、寛容と偏狭、人間相互の性格や気質の違いが休みなく動き、無数の抵抗が人を成長させ、社会を進化させる。
二人は炭焼き小屋に着く。
四
竹中啓吉は40~45歳にみえ、肌黒く引き締まった身体意志の強そうな顔で山男の態。東京から逃げてきた、あそこはソドムとゴモラで、ここは静かでいいという。無宗教かと問われて人間を信じようとしたと答える。親子でブラジルに行き、農業と塾のようなものをやりたいと言う。松山隆二は竹中にすすめられてうるち黍餅を食べる。
竹中は窯を見に行き、隆二は回想する。松山家は福井県南条郡の北にある干飯崎(かれいざき)の漁師町で三代続く一番の網元。彼は東京の水産教習所に入るが第二次大戦になり徴集されるが結核が判明、二十歳まで生きられないと宣告され、故郷で聖書や仏典、天文、科学、医学書を読み漁るうちに健康が回復する。
昭和35年に台風禍で漁船が次々と遭難、母は乳癌で入院、父は脳出血で急逝。遺族への弔慰金などで家財権利を売り払い倒産した。
五
叔父の高川友佑は破産直前まで奔走したが隆二は愚かしいと思った。遺族たちへの補償は十分ではなかったが倒産を悲しんでくれた。松山船長も中島漁労長もいい人だった。
竹中が戻ってきた。大学の実験で使う特別な炭を焼いている。意義ある仕事なのになぜブラジルに行くのかと隆二が問う。竹中はキリスト教の終末観を知っているかと反問し、広島長崎への原爆投下、水爆実験など世界が滅びる時が迫っていると言う。隆二はそうならばブラジルに行ってもどこにいても同じではないかと問う。おそらくそうだが狭い日本よりも広い土地で死にたいと思わないかと竹中が言う。狭い広いはないのではと言う隆二に、竹中は言い過ぎたようだ、日本にいたくない、広くて青空と緑のあるところで死にたいと答える。
隆二は死ぬことではなく生きているうちのことが大切ではと問う。竹中は東京での防空壕の体験を持ち出しどう死にたいかを語る。人類は4千年前の文化から原子力解放までやった。なんの必要、目的意識があるのか、無目的に破滅まで押し流されるかと問う竹中。人間の反省力や自制心で破滅には至らないのではという隆二に、再びキリスト教の終末観を知っているかと問う竹中は、人間は良き社会にしようとしつつも滅亡に向かって奔走しているとしか思えないと言う。人間には自己保存本能があるという隆二に竹中は、ではなぜ第一次第二次大戦はあったのか、人間はいつも殺しあってきた、人類を救う可能性はない、だから自分は広い青空と緑の見える野で死を待つと言った。
この人は逃げようとしている、現実に当面する気力がないだけだと松山隆二は思った。
横になると東京に行くという隆二に竹中は「あそこはソドムとゴモラだ」「すぐに逃げ出すだろう」と言う。故郷の出来事を聞かれるがはぐらかし答えない隆二。先月母は死んだ。どこに暮らしても邪淫と悪徳の世界なら、人間は汚辱の中で生きることができ、なにかと為そうという勇気を持つのでないか、東西の神話はみな混沌から始まっていると思う隆二。
一緒にブラジルにいかないかと誘う竹中に隆二は答えない。竹中は「もう眠っちまったのかな」「若い者は暢気なもんだな」と独り言を言う。
六
林の木々はそれぞれ個性を持っている。しかし隣の木には理解されずに何百年も続く。人間も心の底まで理解しあうことはできないだろう。しかし愛も憎しみも人を信頼することも不信も、ぜんぶふっくるめたものが人間だ。そして闘病を生き抜いた母のことを考える隆二。
迎えに来たりつ子は隆二をせんせいと呼び一日で痩せた、一緒に東京に行きたいと言う。親子一緒がいいという隆二に父は新しいおっかさんと結婚する、私はその人が嫌いだとりつ子が答える。
あくる日の午後、竹中が炭を背負って帰って来た。油屋の親方が来ていて酒を飲んでいる。親方はブラジルに行くと言う竹中にあれこれ詮索するが「はらがへってるんですぐめしにしたい」と答える竹中。「飢え飢え」と思う隆二。おれは飢えていた。それをこの少女に助けられた。人を助けられる状態ではないのにどうしてそんな気持ちが起きるのだろうかと。どこに行っても生活は楽じゃないという油屋の親方に、それは現在の状態を変えたくないだけの気持ちだという竹中。人は住んでいる場所に根を据えたいのだと返す油屋の親方。
隆二は人が人を嫌い、好き、愛し憎悪する本質は何かを考えている。東西の神話、ロシア革命、ソ連も人間性のなにを確かめることができたのか。このままここで暮らそうか、そうすればりつ子はどうなるのか、そんな暮らしはできないと思う隆二。
七
隆二は自然の偉大な力を感じながら東京に向かって仏峠を歩いている。形を変えて生きている自然、永遠につながるものは一つを除いて何もない。人間はプルトニュームを創り出し水素爆弾で地球を破滅できるが征服も破壊もできない。人間の悲しみや絶望、喜びや貧窮、戦争や和平、悪徳や不義の中にも自然の脈動や呼吸は生きている。破壊と大量殺人が繰り返されるのは人間の意志が説明できない未知の力に支配されているからだと。神々よ、私が必要ならば私を生かし力を貸してくださいと願う松山隆二。
「お兄さん」と突然後ろから声をかけるりつ子。驚いて振り向く隆二に一緒に東京に行くために先回りして待っていたと告げるりつ子。戸惑うが二人で東京に行くことになった。さりげないふれあいに本能的に女を感じるりつ子と隆二。
隆二にアメリカの潜水艦と二条の魚介の航跡、潜水艦の砲撃を浴びた時の恐怖がよみがえる。
陽だまりの窪地で焼きむすびを食べようとすると老人に追い払われる。
川には魚がいた
一
河原で焼きむすびを食べる二人。
なぜ追い払われたのかと聞くりつ子に、老人は自分の所有地を誇示したかったのだと答える隆二。涸沢と違って暖かいというりつ子。
川に沿ったり離れたりしながら里に下りていく二人。
東京本所で紙箱工場で働く小学校時代の男の子の友達を訪ねるというりつ子。
途中で出稼ぎに行く様子の百姓らしい男達が追い抜いていく。
農家に泊めてほしいと頼むが断られる。教えてもらった藁小屋に泊まることにして夕飯の準備をして食べる。藁小屋の持ち主の男が現れて追い出される。
二
六キロほど坂下にあった藁小屋に入って二人は寝た。
寒さに耐えるため密着して寝る二人。
翌日は川に沿って下り野口という村で昼飯を食べる。
川に入って魚を捕り、焼いて食べた。
日本の近海から魚類がいなくなり、インド洋やアフリカ、地中海まで漁労に出るようになった。
(朝日新聞日曜版 昭和42年1月~2月 8週掲載で絶筆)
関連用語・事績
ソドムとゴモラ旧約聖書の一つ『創世記』において、ヤハウェの裁きによって天からの硫黄と業火によって焼き尽くされた町とされている。
ソドムの罪は他者への不寛容と同性愛(不自然な肉の欲の満足を追い求めたこと)との説が有力である。
ヨブとサタン【ヨブ記】
旧約聖書の一つである『ヨブ記』。
神から信仰心が篤いと言われているヨブは本当に純真な信徒なのかをサタンが試そうとする。 サタンはヨブから財産、子供を奪い、皮膚病にしますが、ヨブは甘受として受け入れます。 ヨブは訪ねてきた3人の友人に生まれてこなければよかったとこぼします。 悪い行いはしていない、なぜこのような境遇になっているかと主張します。
そこにエリフが現れ、ヨブの誤りを指摘すると神が現れます。
天地創造をした神にヨブはひれ伏し、神は3人の友人にヨブに贈り物をするように命じます。 ヨブは多くの財産を得て、子供を授かり、長寿を果たしました。
浄土真宗
真宗、一向宗とも呼ばれる。大乗仏教の宗派のひとつで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で、鎌倉仏教の一つである。 鎌倉時代初期の僧である親鸞が、その師である法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教え(浄土宗)を継承し展開させる。 親鸞の没後に、その門弟たちが教団として発展させた。真宗10派のうち本願寺派が浄土真宗を公称している。
一向宗
浄土真宗の別称。そもそもは鎌倉時代の浄土宗の僧・一向俊聖が創めた仏教宗派。 江戸幕府によって時宗に強制的に統合されて「時宗一向派」と改称させられた。 さらに江戸幕府によって強制的に浄土真宗の公式名称とさせられた経緯がある。
この作品では時代的に見て浄土真宗を指して用いていると思われる。
禅宗
禅宗とは坐禅の修行を重んじる仏教一派を指す。ただし禅宗という宗派はなく、日本においては臨済宗、曹洞宗、黄檗宗の3宗派をまとめて禅宗と呼んでいる。
永平寺
福井県吉田郡永平寺町にある曹洞宗の仏教寺院。總持寺と並ぶ日本曹洞宗の中心寺院(大本山)である。山号を吉祥山と称し、開山は道元、本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏である。
真言宗
真言宗(しんごんしゅう)は、空海(弘法大師)によって9世紀(平安時代)初頭に開かれた大乗仏教の宗派で日本仏教のひとつ。
真言密教の「真言」とは「仏の真実のことば」を意味し、この「ことば」は人間の言語活動では表現できない、この世界やさまざまな事象の深い意味、すなわち隠された秘密の意味を明らかにしているとされる。
隠れキリシタン
江戸時代に江戸幕府が禁教令を布告してキリスト教を弾圧した後も、密かに信仰を続けたキリスト教徒(キリシタン)。
1873年(明治6年)に禁教令が解かれて潜伏する必要がなくなっても江戸時代の秘教形態を守り、カトリック教会に戻らない信者もいた。
本作品に登場する「隠れキリシタン」がこれに該当するのか、なぜ昭和30年代に独自の秘教形態の信仰を続けている設定なのかは判然としない。
ブラウン運動
液体や気体中に浮遊する微粒子が不規則に運動する現象。1827年にロバート・ブラウンが、水の浸透圧で破裂した花粉から水中に流出し浮遊した微粒子を顕微鏡下で観察中に発見し、論文「植物の花粉に含まれている微粒子について」で発表した。1905年にアインシュタインにより「熱運動する媒質の分子の不規則な衝突によって引き起こされている」という論文が発表された。
水中で浸透圧により破裂した花粉から流出した微粒子ではなく、花粉そのものがブラウン運動すると間違われることがある。
福井県
福井県と原子力発電所福井県には原子力発電所が11基あり、日本で原発が最も多い県である。
強固な敷地の地盤、蒸気を冷やすために必要な水(海水)が大量に確保できること、原子炉立地審査指針に適合する十分広い敷地などの立地条件を満たしていることが必要である。
日本国内における稼働可能な原子力発電炉は33基ある。 原子力規制委員会の審査を経て地元了解も得て再稼働されたものは12基。
総発電量は最大で1,181億kWh(2021年実績は708億kWh)であり、2030年目標の半分程度である。
本作品の執筆当時(1967年)、まだ原発は稼働していないが福井県での設置稼働の検討が続いていた。
関西電力は、原子力発電所の設置を広大な敷地が確保できる点や自然災害が少ないなど、候補地を日本海側は能登半島から丹後半島、太平洋側は紀伊半島を選定していた。
その中で、関西電力は1961年10月、敦賀半島の敦賀市浦底地区と美浜町丹生地区の2か所を調査地点に選定した。
翌年の1962年に、調査対象地点の1つである丹生地区で発電所の開発が進められることになり、日本の電力会社として第1号の原子力発電所の稼働となっていく。
福井県と宗教
福井県は日本国内で浄土真宗の信徒が最も多い県である。
人口当たりの寺院が最も多いのも福井県である。
福井県に浄土真宗の信徒が多い理由として
①浄土真宗の開祖・親鸞が越後国(現在の新潟県)に流罪になり現地でも布教を進めた
②浄土真宗の中興の祖・蓮如上人が福井県吉崎御坊を布教拠点にした
ことがあげられる。
福井県吉田郡永平寺町には曹洞宗の大本山である永平寺がある。
山本周五郎氏がめざしたものとは
周五郎氏は『おごそかな渇き』を通して何を描こうとしたのか。繰り返し読んでみるのだが、残された文章から読み取れることは少ない。今後の展開でどのようにもできるフリーハンドを残したまま断筆になっている。作品以外の場面で周五郎氏自身が語っているものも少ない。
証言を二つ確認してみよう。
まず、周五郎氏自身が綴った文章。
欧米の作家についてももっともうらやましいと思うのは、老年になるときまったようにキリスト教に帰ることだ。一例だけあげてもアナトール・フランスがいる。いちじは共産主義にはしり、ソビエトまでいって来てから、共産主義にそっぽを向き、やはり神の問題に帰ったようである。この小説では、相変わらず貧しい人たちの舞台であるが、その中で宗教と信仰の問題にぶつかってみるつもりである。
特に恵まれた人たちはべつとして、私どもいちばん数の多い人たちは、生活するだけでも常に、困難と拒絶に当面しなければならない。けれども私は、その中にこそ人間の人間らしい生活があり、希望や未来性があると信じている。その中で宗教と信仰がどういう位置を占めているかを探求していきたいと思う。
(朝日新聞 昭和41年12月22日)
特に恵まれた人たちはべつとして、私どもいちばん数の多い人たちは、生活するだけでも常に、困難と拒絶に当面しなければならない。けれども私は、その中にこそ人間の人間らしい生活があり、希望や未来性があると信じている。その中で宗教と信仰がどういう位置を占めているかを探求していきたいと思う。
(朝日新聞 昭和41年12月22日)
周五郎氏自身によるものはこのひとつと言ってよいと思う。
もし他に知っている方がおられたら教えていただけるとありがたいです。
この文章から周五郎氏が目指していた理想はキリスト教的信仰にあると見ることもできるが、そのように断定するには十分とは言えないだろう。欧米の作家だからキリスト教だと考えているとも読めるので、広く別の理想像を描いていたと考える余地も残されている。
いずれにしても、この文章からは抽象的なイメージしか伝わってこない。
「人は生きるなかで直面する困難と拒絶の中に人間らしい生活と希望、未来があるのだ」
と言っている。そして
「その中で宗教と信仰がどういう位置を占めるのか」と述べている。これは実に漠然とした問いかけであって、周五郎氏がどのように考えていたのかということの手がかりすら書かれていない。
周五郎氏本人以外で、かなり踏み込んだ証言を行っているのが木村久邇典氏による山本周五郎全集第16巻「附記」の文章だ。
山本周五郎は昭和三十四年の『五辯の椿』における“裁き”と『ちくしょう谷』での“宥し”、昭和三十六年から八年にかけての『虚空遍歴』や三十八年の『さぶ』における“無償の奉仕”といった宗教的課題に対する傾斜を、年ごとに急速に加速させていった。本編は、作者がわたくしに語ったところでは、ウィリアム・サローヤンの『人間喜劇』に触発されたもので、“現代の聖書”としての小説を構築したいとの意欲のもとに執筆を開始したものである。
この周五郎氏が語ったとされる「『現代の聖書』としての小説を構築したい」という表現が様々な書評などで多く紹介されている。『聖書』という表現だからキリスト教だと断定することはこの時点でもまだ難しいだろう。しかし本文中を含めてキリスト教の考え方や言葉が随所に書かれているのも事実だろう。
加えてこの文章で注目すべきは、昭和三十四年の『五辯の椿』から『ちくしょう谷』『虚空遍歴』、三十八年の『さぶ』にかけて宗教的課題に対する傾斜を年々急速に加速させていったとの考察である。
この考察をみなさんはどのように感じるだろうか。これらの作品を読んで、そこで感じたものが「宗教的課題」と呼べるものにつながっていくと感じた人はどれほどいただろうか。
山本周五郎がいう「宗教」「信仰」とは
そもそもの話でもあるが、周五郎氏が表現している「宗教」とはどのように定義されているのだろうか。
同様に「信仰」とはどのような状態、行為を示しているだろうか。
まずは、小説の主題であると思われる重要なこの「宗教」「信仰」の概念を明確に定義し、定義した意味で使っている言葉であることを明示しなければ話は始まらないのではないだろうか。
同じ「宗教」という言葉を使いながらも、人によってその概念やイメージが全く違っていることも大いに考えられる。というよりも、果たしてどれだけの人が「宗教」「信仰」の具体的な考えを持って、そのイメージなりを周囲の人に説明ができるのだろうか。
私の経験から考えると、身近な友人知人の間では「宗教」の概念は人それぞれで相当に違っていて雲泥の差がある。全く考えたこともない人も多い。
これが現代日本人の実態ではないかと思うのである。
『おごそかな渇き』の不完全燃焼の感は、未完のまま小説の冒頭部分で断筆したことだけではなく、主題の中核を為すと思われる「宗教」「信仰」の概念が漠然としたままストーリーが中断されていることによる部分が大きいと、私は思う。
作品がつづられていく中で、そうした対話が描かれることもあったかもと思うと、残念な気持ちが半分、心待ちだった気持ちが半分、不思議な感覚に包まれるのである。
なお門馬義久氏は「『おごそかな渇き』について」の中で、周五郎の死後に発見された「創作ノート」の内容に触れているが、小説に盛り込む具体的な出来事などのストーリーの展開をメモしたものであって、私たちが最も知りたい「何を書きたいのか」に答えてくれるものではない。

