開催内容 桂冠塾【第158回】
『蒼ざめた馬を見よ』(五木寛之)
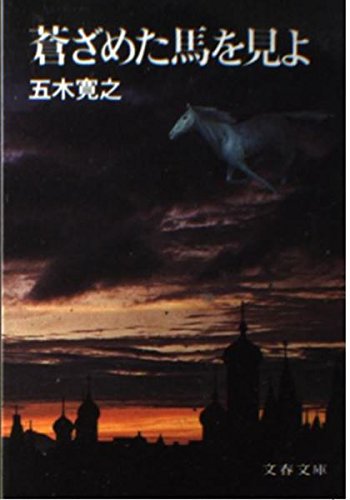
| 開催日時 | 2024年3月30日(土) 10:00~12:00 |
|---|---|
| 開催方法 | オンライン開催 |
開催のコメント。
五木寛之氏の代表作の一つである『青ざめた馬を見よ』を取り上げます。冷戦下のソ連・レニングラード。ある年老いた小説家が人生をかけて書いたとされる原稿を受け取って出版するために、大手新聞社の元記者が日本を旅立った。
ロシア文学を愛する純粋な気持ちが突き動かす熱情なのか、それとも冷戦下で渦巻く政治の陰謀なのか。
日本を代表する作家のひとりである五木寛之氏の直木賞受賞作品を読み進めたいと思います。
作品の概要
作者:五木寛之(34歳の作品)1966年12月発行の雑誌『別册文藝春秋』第98号に掲載
8章で構成される短編小説(原稿用紙換算125枚)
第56回直木賞(1966年下半期)受賞作品
販売部数
1967年 33,000部
1968年 27,000部
1969年 34,000部
1970年 41,000部
1971年 31,000部
1972年 40,000部
などロングセラーになる。
あらすじ
1Q新聞東京本社七階の特別応接室。
論説主幹の森村洋一郎、花田外信部長、外信部記者の鷹野隆介。
論説主幹は鷹野に社を辞めてレニングラードに行く極秘指令を受けてほしいという。
論説主幹から最近亡くなったある高名なロシア文学者からの手紙を渡される。そこには3年前にソ連・ソチの街で偶然に長年翻訳をし敬愛していた老作家M氏と出会い、未公表の長編小説の出版を託されかけたと書かれていた。
その小説にはユダヤ系ロシア人の運命が描かれており、ソビエト文学の至宝ともなるべき作品であった。M氏が「私たちは人間が見てはならない蒼ざめた馬を見てしまったのだ」と語り10年間密かに心血を注いで書き綴った原稿。同時に国家的利益を害するとみなされることも必然であった。自分は保身のためにその原稿を返してしまった。ガンを患い死を直前にしてこの事実を告げ...と手紙は途切れていた。
論説主幹に問われた鷹野は手紙の主は先日亡くなった東野秀行氏、老作家はA・ミハイロフスキイ氏ではと答える。鷹野は未発表の原稿を手に入れるためにソ連に行くことを承諾する。
2
三ケ月後、鷹野はフリーのルポライターとして欧州を経てレニングラードに入った。滞在は一週間の予定だ。翌朝鷹野は策を弄さずにミハイロフスキイの自宅を訪ねた。応対した夫人に3年前に東野氏が果たせなかった依頼を引き受けたいというメモを渡すが会えないと断られる。遅い昼食後、ミハイロフスキイ氏へ接触を取ろうと電話番号を調べて掛けると男性が出るが「ニェート(違います)」と切られた。策を考えながら自分は何のためにこんなことをしているのかと自問する。
3
三日目は雨が降り仕事をする気になれず無為に過ごして夕刻から詩のコンサートに。入場の列に並んでいると民警が来て列の先頭に押し込んでくれて最前列中央に座れた。少年ぽい少女が席を譲ってほしいと言う。街を案内する代わりに席を譲った鷹野はコンサートで叫ぶ少女を見て抱きたい衝動に襲われる。
雨の中を腕を絡ませて歩きレストランに行きビールと食事、ツイストを楽しんだ。少女の名はオリガと言った。ネヴァ河畔を歩き語らい、プーシキンの詩を詠む。互いに普通じゃないところがあるという二人はキスをして別れる。
4
再びミハイロフスキイの電話番号を調べて掛けると女性が出て「ニェート」と答えて切られる。アパートを訪ねるが「主人は会いません」と断られる。鷹野は成り行きに任せようと心を決める。
午後7時にオリガと会うためにデカブリスト広場に行く。タクシーでオリガが友人と借りている古いアパートに行き鰊の酢漬けでブランデーを飲む。二人は絨毯に寝そべって長いキスをする。
その時階下でバケツが転がる音がした。「あの音は嫌いなんだ」と鷹野が言う。<焼き日ですよう>という北鮮の邦人収容所での忌まわしい記憶がよみがえる。その声とバケツの音が満ちると鷹野は発作を繰り返してきた。
鷹野はオリガがモスクワでも見かけたことを告げて何を求めているかと詰問する。無理やり行為に及ぼうとする鷹野にオリガはユダヤ人だと告げるが、鷹野は意に介さず行為を遂げる。かつてオリガを愛したロシア男性はユダヤ人だと告げると突然行為ができなくなった。再び鷹野とオリガは身体を重ねた。日本人はなぜユダヤ人を嫌わないのか宗教はないのかと問う。
二人は行為を終えて少し眠ったあと紅茶を飲みながらそろそろ帰るという鷹野に、オリガは明日はミハイロフスキイ教授のところに7時に行くから少し眠ると告げる。オリガとミハイロフスキイは懇意だった。鷹野はオリガに目的を告げてミハイロフスキイに会わせてほしいと頼む。オリガはその頼みを承諾する。
5
翌日の夜遅く鷹野はオリガとミハイロフスキイのアパートを訪ねた。ミハイロフスキイと対面すると心の内を語り、作者の名前を伏せることを条件に原稿を鷹野に渡し小説の出版を託した。鷹野は翌日の夜までに原稿を一枚ずつカメラで撮影して査証が切れる前日までに23本のパトローネに収め日本大使館のT二等書記官に託して東京に運んだ。
レニングラードを離れる前夜に鷹野はオリガに会い原稿を返すと東京に来ないかと誘うがオリガは断る。仕組まれた出会いだったのかと問う鷹野にオリガは答えず二人は長いキスをした。
6
その年の秋の終わりにQ新聞社出版局から『蒼ざめた馬を見よ』という長編小説が出版された。英語版も出版され欧米の読書界に異常な反響を巻き起こし高い評価を得た。ドイツやリオの雑誌が出版の経緯と真の作者は誰か推測記事を載せた。
その内容は鷹野の行動をほぼ正確になぞっていた。その後9ケ国語で翻訳され映画化も発表された。テレビ、ラジオも巻き込み世界規模のキャンペーンとなった。
7
発刊から3ケ月後の翌年2月下旬にミハイロフスキイが逮捕されて世界を驚かせた。反ソ的な長編小説を国外で偽名で出版し巨額なドルを不正に入手したという理由だった。
表現と出版の自由を叫んで各国の共産党も巻き込んで国際的な署名運動が始まる。反ソビエトの動きも活発化した。
ソ連の機関紙は8月下旬深夜に数名の者で策動があったこと、ミハイロフスキイの部屋の天井裏から数千ドルのドル紙幣が見つかり、出版社からの支払明細書などの証拠品が押収されたが、ミハイロフスキイは一切覚えがない、作品は自作ではないと否認している、事件の発覚は市民の投書で内容は極めて正確だった、この結果ミハイロフスキイは起訴されることが決定したと報じた。
世界中の団体個人がこの裁判を批判し、ソ連は世界で孤立したようにみえた。
鷹野は『蒼ざめた馬を見よ』に違和感を感じていた。ミハイロフスキイが自作だと宣言しないこと、多額のドル紙幣、出版社の書類、オリザの名前が出ないことにも。しかしそのことを忘れようと決心した。
8
裁判が半月後に迫った4月最初の土曜日。鷹野に外人の来客があった。彼は鷹野に一緒に来てほしい、会わせたい人がいると告げる。
彼の運転で外車で移動しながらソビエト文学を語り合う二人。横浜元町に近い高台の古ぼけた洋館に入ると驚愕の真実を目の当たりにした鷹野であった。男からその真実に至る経緯、張り巡らせた陰謀の内幕を告げられる鷹野。その真実を告発するために動いていたその男は対立組織の一員であったが、ミハイロフスキイによって全資料の提出と裁判の弁護の申し出が断れたと告げる。
ミハイロフスキイはこのように語ったという。
「私はこの本を書かなかった。しかし、それ故にこそロシアの作家である私は罰せらるべきだ--」と。
鷹野は部屋を出た。桜木町に走らせるタクシーの中で流れる電光ニュースを見ながらその声をふいに聞いた。
<焼き日ですよう>
<今日は焼き日ですよう-->
それは電光ニュースのかなた、星のない暗い空を群をなして翔けていく、蒼ざめた馬の背後から響いてくる世界の明日を告知する声のように思われた。
関連用語・蒼ざめた馬
『見よ、蒼ざめたる馬あり、これに乗る者の名を死といひ、陰府(よみ)、これに随ふ』(ヨハネ黙示録)蒼ざめた馬はヨハネ黙示録第6章第8節にあらわれる死を象徴する馬。ヨハネの黙示録の四騎士の一つ。
キリストが説く七つの封印のうち始めの四つの封印が解かれた時に現れる。四騎士は、支配する、戦争を起こす、飢饉をもたらす、病・獣によって地上の人間を死に至らしめる、それぞれの権威を与えられているとされる。
第一の騎士
第一の封印が解かれた時に現れる騎士。白い馬に乗っており、手には弓、頭に冠を被っている。勝利の上の勝利(支配)を得る役目を担っていて尊敬を集めるがその勝利は偽りである。そうしたキリストの偽物(反キリスト)が現れるとされている。
第二の騎士
第二の封印が解かれた時に現れる騎士。赤い馬に乗っており、手に大きな剣を握っている。地上の人間に戦争を起こさせる役目を担っているとされる。
第三の騎士
第三の封印が解かれた時に現れる騎士。黒い馬に乗っており、手には食料を制限するための天秤を持っている。地上に飢饉をもたらす役目を担っているとされる。
第四の騎士
第四の封印が解かれた時に現れる騎士。青白い馬(蒼ざめた馬)に乗っており、側に黄泉(ハデス)を連れている。疫病や野獣をもちいて、地上の人間を死に至らしめる役目を担っているとされる。
世界の終末を説いている黙示録には
七つの封印
七つのラッパ
七つの鉢
の順番で人類に災いが起きるとされている。救世主イエスが再臨し、神を信じ正しい行いをした人々だけが復活し地上を1000年間統治する。さらにその1000年後に悪魔が再び現れるが天から炎が降り注いで滅びると書かれている。
ちなみに第五から第七の封印は...
第五の封印 殉教者の魂が現れて神による悪徳者への裁きを求望する
第六の封印 大地震や天変地異が起こる
第七の封印 七人の天使に七つのラッパが渡されて神の裁きが下されていく
となっていきます。
時代背景:東西冷戦
第二次世界大戦後にアメリカ合衆国を中心とする資本主義陣営(西側)と、ソ連を中心とする社会主義陣営(東側)が対立した政治状態を指す。第二次世界大戦の終結直前の1945年2月頃から始まり、ブッシュ・ゴルバチョフ会談が行われた1989年12月で終結したとされているが、その後もベトナム、ユーゴスラビア、アフガニスタン、チェチェン、ウガンダ、ソマリア、イラン・イラクなど多くの紛争が続き、その構図は複雑化している。
東西冷戦はいくつかのステージがあったと分析されている。 始まりは「ヤルタ会談」での戦後国際レジームの対立とみられており、米ソ両大国が互いに自陣営の勢力拡大と相手陣営の封じ込めに狂奔した。
その後
・冷戦のグローバル化時代
・スターリン批判と雪解けの時代
・核開発と宇宙開発競争の時代
・キューバ危機と反戦運動の時代
・デタントの時代
・新冷戦の時代
・ゴルバチョフ改革と冷戦終結
めまぐるしくステージを変遷していった。
『青ざめた馬を見よ』が発表された1966年当時は、1962年のキューバ危機を経てデタント(緊張緩和)の時代を迎えようとしていた。
1963年に部分的核実験禁止条約の締結、1964年に中国の国家承認が行われた一方で、軍拡競争は続いていく。
自由主義国においては東西融和と反共勢力がしのぎを削っていた時代ともいえる。
ベトナム戦争の泥沼化、反戦運動と黒人民権運動の高まりの中で、キング牧師とケネディ大統領の暗殺が続き、社会は混乱を極めていた。
日本においては60年安保闘争を経て70年安保闘争へと向かう騒乱期でもあった。
近年ではシリア、ウクライナ、ガザ、ミャンマー等々、思想対立と強大国による支配の構図は依然として世界中で続いている。
鷹野が告げられた謀略の真実
・鷹野が会った老作家は偽物だった。ポーランド難民が整形手術を受けていた。・世界的に著名な映画監督のR氏が演技指導した。
・オリガは誘導役だった。両親の死の原因がソ連と信じて西側の組織に協力した。
・これはメジチ家以来続く知的な戦争のひとつだ。冷戦融和のムードのいま西側陣営はソ連には自由がないという月並みなスローガンをもう一度叩き込んでおこうとした。
・日本の新聞社を使ってワンクッションを置くことを思いついた。
・ガンで死期が迫っているロシア文学者とソ連老作家を手紙でつなぐ洒落た細工をした。
・秘密裏に転向反ソ連作家のグループを集めてユダヤ人問題の資料を収集した。
・討論システムで作家グループに長編小説を作らせた。
・偽作品の土台はユダヤ系難民の無名作家が書いた某家族の歴史だ。
・ロシア文学者が亡くなった後で偽手紙をQ新聞社の森村主幹に届けさせた。
・大がかりな陰謀を考えついたのが森村論説主幹だ。
・組織の希望通りのジャーナリストが鷹野だった。
・鷹野の申し出を断ったのは本物のミハイロフスキイ夫妻だった。
・ミハイロフスキイはそんな小説を書いていないし東野氏にも会っていない。
・深夜のアパートでは本物の夫妻は寝込んでいた。
・その夜にドル紙幣や書状などの証拠物件を部屋に仕込んだ。
・偽の老作家から偽物の原稿を受け取り、国外に持ち出して出版が行われた。
・その組織は世界の自由主義陣営を聯合した統一戦線的な国際組織だ。
・事実を告げる男は謀略に対応する立場の専門家で、全ての証拠の完全さに疑問を抱き真実にたどり着いた。
・オリガはヘルシンキを発つ前に自殺した。理由は不明。
【読後感】『蒼ざめた馬を見よ』とは?主題は何か。
読了した第一感想は「おもしろい」。 2時間物のサスペンスドラマを見ているような爽快感と、一匹狼の孤独な寂寥感が混ざり合ったような感覚と言ったらいいだろうか。しかし、なんだかもやもやした読後感が残るのはどうしてだろうか...。
まず物語の舞台として東西連戦下で暗躍する自由主義陣営と共産主義陣営との策謀が渦巻いているのは執筆当時の時代背景だと感じる。2024年の現在に身を置いて読むのとは肌感覚が全く違うだろうと。
ソ連がどんな国なのか情報がほとんどない時代。インターネットなんてかけらも存在しなくて、新聞や雑誌で読まれる記事が世論を動かしていただろう。特別な意図を持った情報操作というか情報戦争が社会の裏側で繰り広げられたとしても不思議ではなかった、そんな時代だったのだと思う。自分自身が学生だった頃の経験からも容易に想像できる。
私自身が学生生活を送っていたのは1980年代前半。作品執筆から15~20年後にあたるが、その時代でさえもソ連はベールに包まれた存在で国家スパイの暗躍は当然のように語られていた。
そんな時代に書かれた小説であることを念頭に置かないと、当時の絶賛とも言える高い評価は理解しがたいと思われる。
正直な感想としては「読み応えのある小説だけどそんなに賞賛されるほどでもないかな」。
登場人物の心理描写に感銘を受けるわけでもなく、読者の意表をつくほどのどんでん返しがあるわけでもない。そのように書くと上から目線での感想と言われそうで、実際にはこのような小説を書ける文才もないので怖気ついてしまうのだが、それほどに発表当時の評価は非常に高い。誰もが無条件に、手放しで、大絶賛している。直木賞の選評などを見るとその一端がわかると思う。選考者満場一致での受賞である。辛口の批評は誰からも出されていない。
タイトルの『蒼ざめた馬を見よ』。
ヨハネ黙示録の逸話から想起された言葉であることは間違いないが、正直に言うとしっくりこない。
なぜこのタイトルなのか。
そもそもこの小説のテーマは何なのだろうか。
「蒼ざめた馬」は地上の人間を死に至らしめる役割をする騎士を運んでくるのだから、いま何か目の前で見ているものが死を運んできている、それを私たちは目撃している。そんな意味がタイトルに込められていると言えるだろうが、ではその運ばれてきている「死に至らしめるもの」とは何を指しているのだろうか?
・陰謀集団によって発表された小説『青ざめた馬を見よ』なのか。
・陰謀を企てた謀略集団の存在なのか。
・その謀略によってまんまと思想操作されている世間の有識者たちなのか。
・その情報操作に踊らされている民衆自身なのか。
・自由主義思想と共産主義思想に分かれて対立紛争を繰り返す政治家たちなのか。
・これらの事件に巻き込まれて裁判で判決を受けるミハイロフスキイのことなのか。
・はたまた何も知らされずに正義だと思って駒のように使われた鷹野のことなのか。
・人間の生命の奥底に巣食う他者の生命を奪ってしまう魔性を指しているか
・それらを全部ひっくるめて大きな暗闇の中に突き進んでいこうとしている人類と世界そのものなのか...。
そしてそれを「見よ」とはどのような意図なのだろうか。
それは読者の想像に任されているという言い方もできるだろうが、作品全体から推察できる伏線がなければ薄っぺらい通俗小説と紙一重だと言えるだろう。
小説の中で、登場する小説名のほかに「蒼ざめた馬」と書かれているのは、一つは陰謀の中でミハイロフスキイが語ったとして手紙に書かれている一節
私たちは、人間が見てはならない蒼ざめた馬を見てしまった世代なのだ。それは数限りない死の影です。
もうひとつは最後の一文である。
それは電光ニュースのかなた、星のない暗い空を群れをなして翔けていく、青ざめた馬の背後から響いてくる世界の明日を告知する声のように思われた。
五木寛之氏自身はソ連についても造形が深いという指摘があるので今一歩踏み込んだ別の作品も書いてほしかったと思う。
真実にたどり着いた集団は裁判に真実の証拠を提出する動きに出ていたが、その動きにはストップが掛けられた。ミハイロフスキイの無実が証明されると、その時点までミハイロフスキイが反ソ的作家だと糾弾していたソ連文化界の権威が失墜するからだろうと男は推察していた。政治判断の極みと言える非人道的判断がなされたことになる。
ミハイロフスキイが有罪になっても無罪になっても共産主義陣営は大きな打撃を受ける構造になっていた。「自由、という一つの観念を餌に仕かけた世界を包む巨大な罠」であると。
ちなみにこの真実にたどり着いた集団は共産主義陣営のチームと考えるのが妥当だが、明確に断言されていないのでそうでもない余地も残されていると思う。自由主義陣営側で陰謀的手段を快く思わないチーム、政治とは関係なく純粋に犯罪を憎むオンブズマン的な集団、文化文学を政治利用されないように抵抗する文化人集団、東西陣営の融和を強く望んで行動する集団なども想定されるだろう。
結局ミハイロフスキイは何も知らないままに陰謀に巻き込まれて、おそらく有罪判決を言い渡されることになる。無実の老作家を誰も助けることができない。ミハイロフスキイの身代わりにされたポーランド難民の男も同様だ。
全くの悲劇だ。
そして、ここで大きな意味を持たせているのはミハイロフスキイ自身がこの冤罪を受け入れたことだ。
ミハイロフスキイは言う。
「わたしは、この本を書かなかった。しかし、それ故にこそロシアの作家であるわたしは罰せられるべきだ」
あえて確認しておくがミハイロフスキイは何ら犯罪を犯していない。ただ心の内で感じていた政治への心情を公にすることがなかっただけだ。しかしその行動を起こさなかったことが罰を受けることに値するとミハイロフスキイは結論付けたのだった。
この小説のクライマックスとも言えるかもしれない。
だがこれが五木氏が考える作品の主題だったのだろうか。
物語の伏線となった北鮮の邦人収容所での原体験も気になった。
<焼き日ですよう>
<今日は焼き日ですよう-->
<今日は焼き日ですよう-->
それは、見てはならないものを、あまりにも早く見てしまった少年の、後遺症のようなものだった。
五木氏にとって忘れることができない、でも忘れてしまいたいのかもしれない、自身のアイデンティティの奥底に横たわっている一生無くなることがない泥沼に叩き落された魂の叫びなのかもしれない。
その後、五木氏は精力的に数多くの作品を書き続けてきた。その分野は多岐にわたるが、年齢を重ねるとともに日本人の信仰心に触れる作品や行動が多くなっていったと感じるのは私だけだろうか。
五木寛之氏の作家としての評価が為されるのはもう少し先なのかもしれない。

